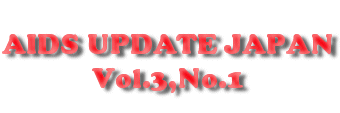 |
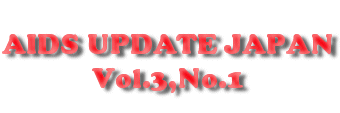 |

|
|||
| はじめに | |||
| 平成12年度厚生省「HIV感染症の医療体制に関する研究班」(主任研究者:白阪琢磨国立大阪病院医長)の中に、「カウンセリング体制の充実強化に関する研究」グループ(以下、本グループ)が発足し、カウンセリング(心理社会的相談援助)を専門とする心理職、福祉職、精神科医合計30数名が6つの研究課題に取り組みました。本稿では、本グループの研究成果を簡潔に紹介します。読者の皆様がわが国のHIVカウンセリングの現状と今後の課題を考えていただくうえで、参考となれば幸いです。 | |||
| 1. 研究の背景と目的 | |||
| HIV感染症の場合、検査前後から末期までカウンセリングが大きな役割を果たすことはよく知られています。ところが、専門的なカウンセリングの担い手である医療領域の心理職及び福祉職の国家資格制度がわが国では未確立のため、感染者が医療保健機関で必ず専門的なカウンセリングが受けられるわけではありません。そこで国は、ブロック拠点病院にはエイズ予防財団リサーチ・レジデント(以下、RR)という形で、拠点病院及び保健所等には都道府県の行政派遣という形で、専門カウンセラーを配置して、感染者や医療関係者のカウンセリング・ニーズに応じようとしています。このような背景を踏まえて、本グループでは、ブロック拠点病院及び拠点病院の専門カウンセラーや派遣カウンセラーがどのようなシステムを構築し、どのような援助技法や研修方法、さらには他職種との連携方法等を確立しているかを把握しようとしました。 | |||
| 2. 6つの研究プロジェクト | |||
| 本グループでは、地域特性や感染状況を考慮し、研究の対象地域を関東圏とそれ以外の地域に分け、それぞれの地域を臨床心理学的な視点と医療社会福祉学的な視点から計4つの研究プロジェクトを組織しました。また、地域を超えて専門カウンセラーを支援する体制づくりをめざし、情報支援ネットワーク構築及び精神科医との連携に関する2つの研究プロジェクトを組織しました。 | |||
| 3. 研究成果の概要 | |||
| (1) 心理職によるHIVカウンセリング体制の現状 | |||
| プロジェクト1では、矢永由里子氏(国立病院九州医療センター)が中心になって、ブロック拠点病院のRRによるカウンセリング制度及び行政によるカウンセラー派遣制度の実態を把握しようとしました。そのために、8ブロック拠点病院のカウンセラー8名と35自治体の派遣カウンセラー等44名を対象に、半構造化面接とアンケート調査を行いました。その結果、心理職を中心に行われている上記2つのカウンセリング制度に、3つの問題構造があることが判明しました。 | |||
| まずは、雇用条件の問題です。社会保険など保障も不十分、勤務形態も不安定、しかも報酬も少ないといった労働条件の悪さが明らかになりました。 | |||
| 次に、制度利用上の問題です。カウンセリング制度を導入したものの医療機関の受け入れ態勢が未整備、医療関係者や感染者がカウンセリングに対する認識が不十分、行政による派遣カウンセラーに対する後方支援が不十分といったことが明らかになりました。 | |||
| もうひとつは、実施上の問題です。これは、面接室等の環境やスーパービジョン体制が未整備であることがわかりました。上記の3点の問題について対処するために、ブロック拠点病院のカウンセラーと派遣カウンセラーが相互連携を活発に行うこと、拠点病院の院内カウンセラーも取り込んだより組織だったカウンセリング体制をつくることなどの改善案が提案されました。 | |||
| (2) 感染者の専門カウンセラーの利用状況 | |||
| プロジェクト2では、山中京子氏(東京都エイズ対策室<当時>)が中心になって、関東圏の感染者を対象にアンケート調査を行い、感染者が心理職を中心とする専門カウンセラー(福祉職、精神科医は除く)をどのように利用しているかを「直接的利用者」の視点から明らかにしようとしました。とくに、専門カウンセラーを利用した問題領域、専門カウンセラーから受けた援助内容を明らかにしようとしました。 | |||
| 具体的には、関東圏の拠点病院及び協力病院36か所で治療を受けている感染者を対象に、専門カウンセラーの利用経験に関するアンケート調査を実施しました。124名の感染者から得た回答を分析した結果、以下の3点が明らかになりました。 | |||
| まず、専門カウンセラーのアクセシビリティあり群の利用経験率は約76%で、そのうち57%がカウンセリングを定期的・継続的に利用していました。次に、専門カウンセラーの利用がもっとも多かった問題領域は、「告知後の動揺」、「仕事・学校での苦労」、「経済的な問題」でした。次に、専門カウンセラーから受けた援助内容でもっとも多かったのは情緒的サポート、次いで福祉制度に関する情報的サポートでした。 | |||
| この結果から、感染者が必要な時に確実にカウンセリングを利用できるためには、感染者本人に対するカウンセラーに関する情報提供のあり方を再検討する必要があるようです。回答した感染者の多くが「生きる意味や人生の振り返り」に関した悩みを抱えているのに、その方面の相談が得意な心理カウンセラーに相談していないという実態は、何とか改善したいものです。 | |||
| (3) ブロック拠点病院のソーシャルワーク機能の分析 | |||
| プロジェクト3では、横田恵子氏(大阪府立大学)が中心になって、ブロック拠点病院におけるソーシャルワーク機能の分析を試みました。関東圏を除く8ブロック拠点病院で、RRあるいは常勤として心理社会的援助業務を行っている心理職や福祉職など11名を対象にディープインタービューを行い、そのカテゴリー分析を行いました。 | |||
| その結果、以下のような現状が明らかになりました。まず、医療専門職集団におけるソーシャルワークの認知と理解が鍵を握っていること、とくにチームリーダーの医師たちが福祉職の専門性を理解していること、RRを始め様々な専門性を持つスタッフがソーシャルワーク機能を果たすことで組織レベルでのサービスの向上に役立っていること、ソーシャルワーク機能を担う者は専任ナースと協働していること、医療における生活問題の増加とHIVケースワークが増加していること、ブロック拠点病院に蓄積された経験を効果的に還元する時期に来ていることなどが明らかになりました。 | |||
| これらの結果を踏まえると、ブロック拠点病院のソーシャルワーク機能は、生活問題を権利や人権の視点で扱えるようなソーシャルワーク的視点を援助者側が獲得する必要があること、ブロック内の当事者組織や医療機関に対してさまざまな働きかけを行うことで、感染者側のエンパワーメントを促進し、医師-患者関係を改革していくことが求められていることなどが明らかになりました。 | |||
| (4) 首都圏の福祉職によるHIVソーシャルワークの実態調査 | |||
| プロジェクト4では、山本博之氏(東京都エイズ対策室)が中心になって、首都圏の医療機関に在籍する福祉職がどの程度HIV感染者への支援経験があるかという現状を把握し、今後の課題を明らかにしようとしました。そのために、東京都医療社会事業協会会員を対象に郵送にてアンケート調査を実施しました。 | |||
| その結果、203名の回答者のうち、「感染者支援経験あり」群66名(32.5%)で、そのうちエイズ診療拠点病院の福祉職の占める割合は7割でした。ただ、一般医療機関の福祉職も約2割を占めていることから、今後様々なフィールドの福祉職が感染者支援を経験する可能性が示唆されました。また、「経験なし」の理由は大多数が「受診がない」と答えましたが、こうした医療機関においても常にソーシャルワーク援助を効果的に提供出来る知識的、技術的な準備を整えておく必要があると思われます。 | |||
| (5) カウンセラー支援ネットワークの構築の試み | |||
| プロジェクト5では、小島賢一氏(荻窪病院)ガ中心になって、専門カウンセラーを支援するための情報ネットワークを構築するため、インターネットを利用した情報流通・交換に関するカウンセラー対象の意識調査を行いました。 | |||
| 具体的には、平成12年1年間にインターネット上で提供されたHIV関連情報に基づいて調査票を作成し、研究協力者らとE-mail交換の実績のある臨床心理士等及びHIVカウンセリングに参画が予定されている者計59名を対象に、E-mailによる調査依頼と調査票回収を行いました。有効回答数は、45名(有効回収率76%)でした。 | |||
| 主な結果は、以下の3点です。まず、経験年数や担当事例数が少ない若いカウンセラーほど幅広い情報を求めました。次に、女性のカウンセラーは、学会や厚生科研のテーマ、疫学関連、女性保護、予防といった問題により強い関心を示しました。次に、男性感染者を多く扱っているカウンセラーほど疫学関連、予防等の情報を高く評価し、異性間性行為経由の感染者を多く扱うカウンセラーほど差別、検査や薬品関連の情報を高く評価しました。 | |||
| この結果から、HIV関連の情報が溢れる中で、当初の予想とは逆に、全体に選択的というより幅広く多くの情報を求めていることが明らかになりました。したがって、今後は情報の重要度や緊急性について目安となる記号を付記して伝達することも必要かと思われます。自由記述で、心理学的知見の情報提供、カウンセラー固有の情報交換の場を求める者が多かったことから、カウンセラー独自の支援方法を模索する必要があることも示唆されました。しかし、ネット上のセキュリティを考えると、独自の情報交換とネットワークについては慎重に進める必要があると思われます。 | |||
| (6) 精神科医と専門カウンセラーの連携によるJHDSの開発 | |||
| プロジェクト6では、平林直次氏(東京医科大学)が中心になって、精神科医とカウンセラーとが連携しHIV痴呆のスクリーニングを行うための日本語版HIV痴呆スケール(Japanese version of HIV dementia scale: JHDS)の開発を行いました。 | |||
| 具体的には、英語版HIV痴呆スケールを邦訳し、これに基づき検査施行の実際をビデオ撮影し、インストラクション用CD-ROMを作成しました。このCD-ROMを研究協力者などに配布し、精神科医またはカウンセラーである調査者にJHDSの施行方法を修得してもらいました。研究の趣旨を説明し同意の得られた感染者32名と対照99名にJHDSを施行しました。 | |||
| その結果、まずJHDS得点は、HIV痴呆(ADC)の有無とだけ有意に相関することが明らかとなりました。対象20名については初回施行から4週間後に再施行し、JHDSの再現性が確認されました。また、JHDSとminimental state examination test (MMSE)の両者を施行した39名については両検査の相関関係を検討し、両検査の得点の間に有意な正の相関関係が認められました。JHDS得点による痴呆のcut off pointを10点とした場合、感度100%、特異度88.7%でした。その結果、JHDSはHIV痴呆の臨床スクリーニングの有効な検査方法であることが示されました。今後は、JHDSを用いてHIV感染者に認められる知的機能低下の全国調査が必要であると思われます。 | |||
| 4. 今後の課題 | |||
| プロジェクト2は、HIV疫学研究班ですでに2年間にわたり研究が行われており、平成12年度が最終年度でした。この研究は、首都圏を中心とする関東圏の拠点病院及び診療協力病院の医師及び感染者を対象に、専門カウンセラーの認知度や利用経験に関する実態調査を通して、医師や感染者による専門カウンセラーの利用をいかに促進するかについて、有効な情報提供が必要であることを繰り返し指摘してきました。 | |||
| とくに最終年度の本年度は、感染者が「告知後の動揺」や「仕事や学校での苦労」では専門カウンセラーによく相談しているが、「生きる意味や人生の振り返り」に関する悩みというきわめて心理的な相談が意外と少ないという重要な指摘を行いました。カウンセリングのユーザーに直接質問するというこの研究は、HIVカウンセリングが比較的普及している首都圏でなければできない研究でしたが、今後はこのようなダイレクトな研究を増やす必要があると思われます。 | |||
| プロジェクト6も、継続研究2年目の研究でした。精神科医とCPが協力してHIV痴呆を早期に発見するためのスケールJHDSの開発が着々と進められています。平成12年度までは都内の数病院を受診している感染者を対象にJHDSを施行しましたが、今後は全国的な規模で標準化のための作業が展開される必要があると思われます。 | |||
| プロジェクト1、3、4、5は、平成12年度からスタートしたばかりで、今後の継続研究のための基礎的、探索的な調査研究が行われました。プロジェクト1及び3は、それぞれ臨床心理学的と医療ソーシャルワーク学的と切り口は異なりますが、ブロック拠点病院を核にした心理的・社会的な援助体制を構築していくために重要な知見を提供してくれることが期待されます。プロジェクト4は、プロジェク2のいわば福祉職であり、HIVソーシャルワークの先進地域である首都圏の福祉職を対象としているだけに、実際の援助経験をもとにHIVソーシャルワークの新たな技法やシステムが今後提言されることが期待されます。 | |||
| プロジェクト5は、従来電話やFAXによって行われていた専門家支援方法を、インターネット上の電子メールやホームページなどで行うというまったく新しい試みです。事前のニーズ調査も、実際の[kojamaNET]と称するカウンセラー向けの情報提供も、その評価もすべてネット上で行われます。迅速かつ容易な方法である一方、個人情報の保護などカウンセリングではとくに配慮及び検討すべき課題が山積しているように思われます。 | |||
| 最後に、本稿の内容に多少とも関心をお持ち頂いた方は、ぜひ白阪班の平成12年度研究報告書に収められた本グループの6編の論文をお読みいただき、かつ忌憚のないご批判ご意見を賜りますようお願いします。 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 今年はエイズ20年にあたります。後から見て「これはエイズだ」と言える症例報告の最初が、1981年6月だったからです。この年表は、エイズコラムニストの草田 央さんのサイトにある「エイズ基礎年表」( http://www.t3.rim.or.jp/~aids/history.html )を元に改編させて頂きました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
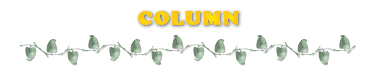 |
||||
|
||||
| ◆ この20年間にエイズウイルスに感染した人は、世界で5600万人を超え、うち2180万人以上が亡くなった。昨年だけでも死者は300万人に上る。一方で、530万人が新たに感染した。 | ||||
| ◆ 世紀をまたいで人類を脅かすこの疫病をどう克服し、ウイルスに感染した人たちの生命や暮らし、人権をいかにして守るか。国連は25日からニューヨークでエイズ特別総会を開き、国際的な行動指針となる政治宣言を採択することにしている。 | ||||
| ◆ 国連はエイズ禍の拡大阻止、とくに若者の感染を減らし、母子感染を防ぐことを大きな目標に掲げてきた。感染者と患者の就労機会の確保や、エイズで親を失った孤児、エイズに感染した子供のケアの重要性も強調してきた。 | ||||
| ◆ にもかかわらず、感染者は増え続けている。治療も行き渡らない。目標達成に必要な行動が遅れているためである。実効ある特別総会にするため、各国とも行動の裏付けを伴う発言に徹してほしい。 | ||||
| ◆ 感染者の約9割は開発途上国に住み、7割強がサハラ以南のアフリカに集中している。国連の推計では、途上国におけるエイズ予防や治療などには、先進諸国からの支援、途上国の政府支出額を合わせて年間90億ドル前後の費用を要する。 | ||||
| ◆ 実際の支出額は年間20億ドル弱に過ぎず、資金不足は覆いがたい。今度の総会を機に、エイズなどの感染症対策として世界保健基金(仮称)を創設する準備が進んでいる。できるだけ大きな基金を積み上げるとともに、途上国の要望に配慮した運用方法を採用すべきだと思う。 | ||||
| ◆ 日本政府は5年間で30億ドルの感染症対策支援を表明し、実行に移した。欧米の先進国と比べても支援額は多い方だ。 | ||||
| ◆ 途上国でのエイズ対策は非政府組織(NGO)との連携抜きでは成り立たない。保健施設整備や医療機材提供といった「モノ」の支援にとどまらず、国内外のNGOともっと積極的に協力する必要がある。 | ||||
| ◆ エイズのワクチンはまだないが、治療薬の進歩で先進国での死亡率は大きく下がった。ただ、薬代が高すぎて途上国では大半の患者や感染者に届かない。 | ||||
| ◆ 薬価が高くなるのは欧米の製薬会社が特許を握っているからだ。自主的に廉価で治療薬をアフリカ諸国へ提供する製薬会社も相次いでいるが、より一般的なルールづくりが必要ではないか。 | ||||
| ◆ 欧州連合(EU)は、エイズ治療薬については特許保護を弾力的に運用することを世界貿易機関(WTO)に提案している。それも一案だ。ぜひとも治療薬の普及を図り、感染者が感染前と同じように社会生活を送れる機会を拡大してもらいたい。 | ||||
| ◆ この疫病には、既存の法制の枠を超えて世界中が総力で取り組まない限り、到底勝てない。各国の指導者は、そのことを肝に銘じなければならない。 |
 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ■ アメリカの保健福祉省とヘンリー・カイザー財団による治療ガイドラインが改訂されました。2001年2月4~8日にシカゴで開催された、第8回レトロウイルスと日和見感染会議で報告され、さらに4月23日に改訂されています。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 今回の改訂版では、以下の点が大きく変わっています。(1)治療開始に関する考え方がガラリと変わりました。(2)アドヒアランスに関する記述を増やしています。(3)参考になる新しい表が加わっています。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ まず治療開始です。従来のガイドラインでは無症候患者でCD4陽性T細胞数が500個/mm3未満あるいは血漿HIV RNA量が20,000コピー/mL(RT PCR法)の場合に治療の開始を勧める積極的治療が薦められていました。しかし抗HIV療法をしていると服薬アドヒアランスが不良で薬剤耐性が発生したり、リポジストロフィーなどの副作用があらわれ、患者に不都合な面があることが明らかになってききました。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ■ 今回、Multi-Center AIDS Cohort Study(MACS)による疾患進行の危険性を検討することにより、「無症候の患者の治療の開始は、CD4陽性Tリンパ球数が350個/mm3未満あるいは血漿HIV RNA量が55,000コピー/mLを超える場合」とされました。データをもとに、治療を遅らせた場合と、早期治療を行った場合の、危険性及び有益性を考慮し患者に注意深くカウンセリングと教育をした上で治療を開始するべきであるとした。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ アドヒアランスの大切さが強調されています。最近は抗HIV薬の副作用を恐れてアドヒアランスが低下する例が増えていると指摘しています。また、医師による患者のアドヒアランスの予測はアテにならないとも書いてあります。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 副作用では、乳酸アシドーシス・急性脂肪肝、そして脂肪代謝の異常で、プロテアーゼ阻害剤を中止したり変更すべきなのかについては、まだデータが揃っていないと記されています。NNRTIでは5%以下だけど、非常に重篤な皮膚障害が起こることに注意を喚起しています。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■ 毎回、相当詳しい解説や表が添付されています。これらを十分に読まないで「HIV感染者だ。抗HIV薬だ。」とすぐに治療を開始することがあります。ほとんどの場合、抗HIV薬は慌てて治療をする必要はありません。慣れない医師は、必ず慣れた医師の意見を求めて頂きたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■ 1994年2月、小児科のエイズ臨床試験グループ(PACTG)プロトコル076の結果、ZDVによる予防療法によって、周産期のHIV-1母子感染を約70%減少させることができることが報告されました。その後HIV-1感染症の病態の理解、およびHIV-1感染症の治療とモニターで大きな進歩があり、標準の抗HIV治療の変化をもたらしました。妊娠時の抗HIV薬剤の使用は、妊婦本人への影響、胎児/新生児への影響、母子感染の予防効果などの考慮が必要です。 | |||||||||||||||||
| ■ この勧告では医療現場で発生するいくつかの場合をシナリオとして分け、母親のケア、母子感染の予防、産まれた新生児のケアについて解説しています。新薬の発売や最近わかった研究成果を元にしており、母子感染予防の戦略も急に変化しています。 | |||||||||||||||||
| ■ この勧告は、アメリカ保健福祉省公衆衛生局によってつくられたガイドラインの最新版です。2000年11月3日(日本語版あり)、2001年1月24日、2001年5月4日と矢継ぎ早に改訂されました。日本語訳が望まれます。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||
| ■ 英国の成人に対する改訂版治療ガイドラインのドラフト(PDF版 150KB)が公開されています。いつ治療を開始するかについては、HIV RNA量は気にせず、CD4数で割り切っている点が、アメリカとの大きな違いです。 | |||||||||
|
|||||||
| ■ アメリカのガイドラインが、成人版と母子版が改訂されたのを契機に、日本でも再検討され改訂に至りました。第4版が発行されたのは2000年11月のことで、1年もたっていません。改訂の基本認識はアメリカの影響を強く受けています。しかし説明文には研究会の工夫がかなり入っています。 | |||||||
| ■ 今年も、日本エイズ学会総会で本会主催のサテライトシンポジウムが企画されています。抗HIV療法について多くの人が参加して公開討論できる貴重な機会です。本てびきの発行部数は3万部とも4万部とも言われていますので、日本の医療界ではベストセラー(非売品ですが)になるのではないでしょうか。 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||
| ■ 強力な抗HIV薬の併用療法が開始され、免疫能が改善されてくると日和見感染症の二次予防、一次予防の継続が不必要と考えられるようになりました。このため蓄積されたデータを参照しながら、以前の治療指針を改編することになったのです。不必要な治療を中止することは、治療自体を単純にしますし、薬剤の副作用を減らし、抗HIV療法自体の服薬も容易になり、医療費も安くて済みます。 | |||||||||||||
| ■ 表は13あります。文末の付録の中には、HIV感染者が日和見感染症の病原体に曝露されないために、性行為、注射薬、環境や職業、ペット、飲食物そして旅行先での注意などに関する記述がついています。 | |||||||||||||
| ■ この草稿は、アメリカ保健福祉省公衆衛生局とアメリカ感染症学会の共同編集によっています。1999年に発行された前書(MMWR 1999;48:No. RR10))の改訂版です。広く意見を求めるために公開されました。意見は2001年9月1日までにNIHの臨床部Henry Masur医師に届けるよう求めています。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■ 2001年の6月29日に最新版が発表されました。アメリカの医療従事者が職業上でHBV、HCV、HIVを含む血液や体液に曝露されることを管理する勧告の最新版です。 | |||||||||||||||
| ■ HBVの曝露後は抗体陰性者にHBIGやHBVワクチンを使用することが上げられ、その効果を確認する必要があります。HCVへの曝露の場合は定期的な経過観察が推奨です。HIVについてはこれまでの考え方を改編しています。基本的な薬物療法は核酸系逆転写酵素阻害剤を2剤投与することで、危険度が高いものについて3剤目を追加することになっています。以前のAZT+3TC+IDV(NFV)と固定したものではなく、選択できる薬剤の幅も広がっています。 | |||||||||||||||
| ■ 治療開始が遅れる場合、原因となる人の感染症の有無が不明の場合、薬剤耐性の場合、治療の副作用の問題などが解説されており、曝露後予防ホットラインが紹介されています。ガイドラインの後には、卒後研修認定用の自習問題集もついています。 | |||||||||||||||
 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【背景】 | |||||||||||
| ヒト免疫不全ウイルス1型(HIV-1)に感染した男性と女性において、血漿中のウイルスRNA量(ウイルス負荷量)に差があるのかどうかについては明らかにされていない。男性では、セロコンバージョン後の初期ウイルス負荷量によって、後天性免疫不全症候群(AIDS)に進行する可能性を予測することができるが、女性では、この二つの関係については評価されていない。そのため、現在は、女性にも男性にも一様に、抗レトロウイルス療法の開始に関するガイドラインが適用されている。 | |||||||||||
| 【方法】 | |||||||||||
| 1988~98年にわたって、HIV-1セロコンバージョンが確認された後、前向きの追跡調査を行った薬物注射の常用者の男性156例と女性46例に対して、その後約6ヵ月間隔で、ウイルス負荷量とCD4+リンパ球数の測定を行った。 | |||||||||||
| 【結果】 | |||||||||||
| 初期ウイルス負荷量の中央値は、男性が50,766コピー/mLであったのに対して、女性は15,103コピー/mLにすぎなかった(p<0.001)。これに対して、初期のCD4+数の中央値には、性別による有意な差は認められなかった(男性と女性のそれぞれで、659細胞/mm3、672細胞/mm3)。HVI-1感染からAIDSへ進行したのは男性が29例、女性が15例であり、AIDSへの進行のリスクにも性別による有意な差は認められなかった。ウイルス負荷量が1 log(底を10とした対数スケール)増加するごとのAIDSへの進行のハザード比は、男性が1.55(95%信頼区間、0.97~2.47)、女性が1.43(95%信頼区間、0.76~2.69)であった。初期ウイルス負荷量の中央値をAIDS発症の有無によってみてみると、血漿1mL中のHIV-1 RNAのコピー数では、AIDSが発症した男性が77,822 コピー/mLであったのに対して、AIDSが発症しなかった男性では40,634コピー/mLであった;これらに対応する女性の値は、17,149コピー/mLおよび12,043コピー/mLであった。したがって、ウイルス負荷量が20,000コピー/mLに達したら治療を開始すべきであるという勧告では、今回のわれわれの研究に参加した男性の74%が、セロコンバージョン後の最初の来院時に治療適格例になるのに対して、女性の治療適格例は 37%にすぎない(p<0.001)。 | |||||||||||
| 【結論】 | |||||||||||
| 初期のHIV-1 RNA量は、男性よりも女性で少なかったにもかかわらず、男性と女性のAIDSへの進行率は同程度であった。したがって、CD4+リンパ球数ではなくウイルス負荷量に基づいた治療ガイドラインでは、抗ウイルス治療を受けられる患者の適格性に性別による差が生じてくるはずである。 | |||||||||||
| <コメント> | |||||||||||
| ■ 男性と女性でHIV RNA量が歴然と違うと言うショッキングな報告です。もちろんアジアでもアフリカでもそうなのか、追試が必要かもしれません。 | |||||||||||
| ■ CD4数の推移は男女差がなかったというので、ちょっとホッとしました。HIV感染症の評価の目安として、CD4数とHIV RNA量をここ数年間、私たちはアテにしてきました。その考えがガラガラと崩れてしまうことはなさそうです。 | |||||||||||
| ■ 今後どんな影響を与えるでしょうか。ひょっとしたらHIV感染症治療ガイドラインの設定を男女別に作っていく必要が出てくるかもしれません。日本の女性のHIV感染者については、社会心理的な検討が始まったところです。HIV感染症自体の医学データについて、全国で集め直してみるべきかもしれません。[TAKATA] | |||||||||||
● 2001年3月9日緊急収載
|
 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
| このWebサイトは厚生科学研究費補助金に基づく「HIV感染症の治療に関する研究」の一環として開設されたもので、HIV診療に携わる医師を対象として、抗HIV薬の血中濃度測定の依頼を受けつけています。 | ||||||
| □測定できる薬剤 | ||||||
| プロテアーゼ阻害剤: | ||||||
| インビラーゼ(SQV)、クリキシバン(IDV)、ノービア(RTV)、ビラセプト(NFV)、フォートベイス(SQV)、プローゼ(APV) | ||||||
| 非ヌクレオシド系 逆転写酵素阻害剤: | ||||||
| ストックリン(EFV)、ビラミューン(NVP) | ||||||
| □主治医の登録 | ||||||
| IDとパスワードの発行を受けなければ、測定を依頼することができません。まず研究グループのウェブサイト( http://www.psaj.com/ )に行って、画面の指示に従い依頼者の登録を行います。数日中にIDとパスワードがメールで連絡されてきます。 | ||||||
| □依頼の手順 | ||||||
| 次に、測定依頼画面(またはFax)で、血中濃度測定依頼申請書を国立大阪病院薬剤部に送ります。すると後日、国立大阪病院からプロトコールと患者ケースカードが、検査依託会社の(株)BMLから採血管と依頼伝票が送られてきます。なお、初めての申し込みの際は、採血方法や回収手順等についてBMLから連絡がある場合があります。 | ||||||
| 主治医は採血管に患者検体の採血を行い、血漿を分離して凍結します。検体の回収を最寄りのBML営業所に依頼し、検体を引き渡します。また国立大阪病院に患者ケースカードを送付します。BMLから、主治医と国立大阪病院に検査結果の報告が行われます。 | ||||||
| □その他 | ||||||
| 検体の送付、測定の費用は研究班が支払いますので、依頼者や患者さんのご負担はありません。また患者名は記号化して扱われプライバシーは保たれます。 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ■ この研究班(主任研究者:福武勝幸東京医大教授)は不特定多数を対象に薬剤を配布しているのではなく、薬事法の定める事項を遵守し、研究班の目的と規定にもとづき国内未承認薬(海外の承認薬)を用いた臨床研究を行っています。以下、トピックスの記事から引用・転載します。詳しくはこのホームページの本文をご覧になり、必要な書類をダウンロードしてご確認下さい。 | ||||||||
|
|
||||||||
| ■ エイズ治療薬研究班では薬剤耐性を獲得した感染者の治療を充実させることを目的に、保険診療が認められていない薬剤耐性検査による薬剤選択法を用いた治療を研究することになりました。その結果を評価することにより、将来の保険適応の可能性も考慮されています。なお、耐性検査の費用は研究班の負担ですが、その他の検査や薬剤などについては保険診療となります。 | ||||||||
| ■ 対象は最近の血中HIV‐RNA量が1000コピー/ml以上で、薬剤の変更が必要と考えられる症例50例です。検査はエスアールエル株式会社へ委託し、VIRCO社においてGenotype Assay とPhenotype Assayを行います。また国立感染症研究所において研究開発が進められている耐性検査を同時に実施します。検査結果は各担当医師と研究班事務局へ返送され。担当医師は検査結果をもとに治療を変更あるいは継続します。関係者が多いので、必ずフローチャートを参照してください。 | ||||||||
| ■ ジェノタイプ(Virtual Phenotype)、フェノタイプ(Antivirogram)の説明はVirco社ホームページをご覧下さい。( http://www.vircolab.com/ ) | ||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ■ エイズ治療薬研究班は、「HCV+HIVあるいはHCV併発血友病患者に対するインターフェロンα-2bとリバビリン併用投与による治療研究」としてC型慢性肝炎の治療研究を開始します。リバビリンはインターフェロンとの併用によって、C型慢性肝炎の治癒率を向上させることが欧米の治験であきらかとなり、既に欧米にて承認されています。 | ||||||||
| ■ 目的はリバビリンとIFNα-2b(イントロンA)併用投与の有効性と安全性を検討することです。対象は血友病患者(血友病類縁疾患も含む)のうち、HIV感染とC型慢性肝炎の両者併発、あるいはC型慢性肝炎のみを発症している症例です。治療薬研究班よりリバビリンを無償で供給し治療研究を行います。C型慢性肝炎のみの群と、HIV感染とC型慢性肝炎の両者を併発する群を比較することにより、本併用療法の有効性・安全性に対するHIV重複感染の影響を検討します。 | ||||||||
| ■ 調査方法、投与方法のプロトコールは欧米での投与基準ならびに日本で行われている治験の方法を基準にして作成しています。なお、インターフェロンα-2b(イントロンA)は市販品を使用し、保険診療として投与して下さい。エイズ治療薬研究班からインターフェロンα-2bは供給しません。 |

|
|
|
|
|

|
|
|
|
| ■ 日本の医療現場に心理的なサポートが加わったのはいつからでしょうか。精神科医療そして小児科医療の中に、その歴史は刻まれているようです。WHOはエイズ/HIV感染症の領域でのカウンセリングの重要性を指摘し、エイズ予防財団は厚生省の委託を受けて全国規模や地方レベルでカウンセリングの研修を展開してきました。日本臨床心理士会のHPに、経緯の概観と歴史が記されています。 |
|
|
|
|
| ◆ 国際エイズ協会が、7月8~11日、アルゼンチンのブエノスアイレス市で「第1回HIVの病態と治療に関する国際会議」を開催しました。 |
| ◆ Medscapeにカンファレンスの報告が掲載されています。 |
| http://hiv.medscape.com/Medscape/CNO/2001/IAS/public/Conference.cfm?conference_id=124 |
| キーワードを入力すると結果が出力されそれぞれ、内容を確認できます。 |
|
|
||
|
|
||
| ■ エイズの業界が広がっていきます。昔は"ウイルス"とか"抗体"の解説をしていました。ところが現在では"ミトコンドリアのDNAは・・・・"という解説が必要な時代になりました。新規参入する研修医の人たちをカバーしなければならなくなりました。このため「不正確でもわかりやすい」解説から、「なるべく正確にわかる」にシフトしてしまい、小難しい表現になってしまいました。 | ||
| ■ ケア提供者、エイズNGOを対象に残部をおわけしています。ご希望の方はご連絡下さい。 | ||
|
|
|
|
|
| ■ ウェブを通じて書き込んだり、訪問調査を受けることで病院機能評価機構の評価を受けるというものです。 |
|
|
|
|
| ■ 多くの抗HIV薬は日本での臨床試験を短縮して早期導入されました。データは外国のものを利用したのです。民族差や体重による差があるかもしれません。このため厚生省は市販後全数調査を10年間実施するようメーカーに命じました。調査項目も、新薬申請の臨床試験と同じような細かな臨床データを全部拾い上げるようになっています。 |
| ■ 従来なら、医薬品ごとにデータを集めていました。抗HIV薬は一人の患者に複数の新薬を使うので、薬剤ごとにケースカードを作ると重複します。1年につき1枚のケースカードを10年書き続けることは大変です。1枚のカードを書くには数時間かかります。HRDでは無駄な手間を減らすために、1患者1ケースカードとして、調査も医薬品メーカーではなく、専門のアルトマーク社が一括して受注しています。 |
| ■ HRDのサイトは、いやになるほど面白くない作りです。HRDの調査報告書などが掲載されていますが、全部pdf版で、ダウンロードしなければ内容がわかりません。また検索もできません。これが、情報公開といえるのかなぁと思います。全社が集まって共同調査協議会を作って話し合っているとありますが、改善するつもりはないのでしょうか? |
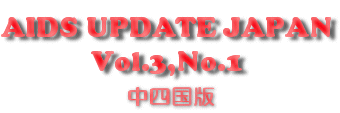 |
|
| 1.HIV感染症の治療の考え方が変わってきた | ||||||||||
| ● エイズは確かに慢性疾患になったけれど | ||||||||||
| 1996年のプロテアーゼ阻害剤の導入と多剤併用療法によって、HIV複製を抑制すると、低下の一途であったCD4細胞数が回復し、日和見感染症を起こさなくなり、エイズを発病しなくなりました。発病者のあるものは社会生活に戻り、死亡者数も減少しました。HIV感染症・エイズは診断されたら死を覚悟する病気から、典型的な慢性疾患に変貌したことは間違いありません。ところが、新しい問題が出てきました。 | ||||||||||
| ● ウイルス学的な治療失敗が多い | ||||||||||
| 抗HIV薬を投与してHIV RNA量を検出限界以下に低下させることができない、あるいは一旦消失させたHIV RNA量が再度上昇してくる場合を、「ウイルス学的な治療失敗」と定義しますと、残念なことに約半数の患者さん達が"失敗"になってしまい、愕然としました。この原因は、私たちのHIV感染症の理解や薬が未熟で、相手のHIVが手強いということでしょう。確かにまだ理想的な薬はありません。副作用はもちろん、剤型、カプセル数、大きさ、臭いや味などにも大きな欠点を残しています。そして薬剤耐性HIVの問題が大きくなってきました。 | ||||||||||
| ● 医師は治療を強要していないだろうか | ||||||||||
| 患者さんが薬を飲む覚悟ができないのに、医師が「この病気は治療が必要だ」と、無理に治療を開始してしまうことがあります。間違った処方をすることもあります。数や服用のタイミングなどの基本的な間違いのほか、併用で使われる他剤との薬物相互作用の問題もあります。医師は万能者ではありません。 | ||||||||||
| ● ふりだしに戻れない | ||||||||||
| 患者さんに詳しく話を聞いてみると、必ずしも処方通りに薬を飲んでいない、飲めていないと言う実態がかなりあります。抗HIV薬の飲み忘れる率が高いほど、耐性ウイルスの発生率が高いという報告があります。逆に成功している人の話を聞いてみたら、確かにきっちり飲んでいることが多いです。失敗した患者さんが「今度からきちんと薬を飲みます。」と覚悟したときには、「耐性になったのでもう遅い」という悲しい現実も経験されるようになりました。耐性がすぐに病気の進行に結びつくわけではありませんが、ウイルスが消えないことは爆弾を抱えたような生活です。 | ||||||||||
| ● 患者さんの決意を待つこと | ||||||||||
| 大切なことは初回、患者さんが治療を開始できる状態になるまで待つことです。治療は何年も続くのですから、急がないで下さい。まず治療についての十分な情報提供が必要です。その上、周囲の人の支えや経済的な問題を含めた社会的心理的な安定が必要です。これは医師と患者、看護者と患者だけの関係では達成できないかもしれません。心理や福祉の専門職、そして患者さんの周囲にいる人たちの援助も必要です。 | ||||||||||
| 2.HIV感染症のケアはチーム医療 | ||||||||||
| ● 薬には薬のプロが必要だ | ||||||||||
| 中国四国地方の58のエイズ拠点病院に勤務する医師の数は6,700人です。誰が抗HIV薬を処方するかわかりません。全員の医師が抗HIV薬に詳しくなることは不可能です。処方箋を受けとる薬局に抗HIV薬に強い薬剤師がいれば、その人がチェックをすることができます。量や服薬のタイミング、他の薬との飲みあわせ、そして医師や患者さんへの情報提供ができます。薬剤師が患者さんと面談して、「この患者さんは、お医者さんの圧力で治療を了承したけど、本当は薬を飲むつもりはない、飲めない。こんな時に治療をするのは危険だ。」とわかることだってあります。 | ||||||||||
| ● 薬剤師もエイズの治療チームの一員に | ||||||||||
| ここで、薬についての専門家である薬剤師が登場しない理由はないでしょう! 最近は病棟の服薬指導業務についている薬剤師が増えています。HIV感染症の薬物療法は、薬剤師の職能を十分に発揮する絶好のモデルであると言えます。HIV感染症・エイズ治療のチームの中に、薬剤師さんたちの参加を強く希望し迎え入れましょう。 | ||||||||||
| ● 薬剤師の対人コミュニケーション | ||||||||||
| 医学教育と同じように日本の薬学教育にも大きな問題がありました。これまで薬というモノに対する教育ばかり重んじてきたように思えます。患者さんと接するのは現場に出てから、経験を積んで体得すればよいという考えです。しかし教育も変わらなければなりません。対人コミュニケーションの知識や技術についての教育と訓練が必須です。私たちは「抗HIV薬服薬指導のための研修会」を行ってきました。HIV感染症に絞ってみますが、課題はおそらく共通すると思います。 | ||||||||||
| 3.抗HIV薬服薬指導のための薬剤師研修 | ||||||||||
| ● 3年間でのべ164人の参加者 | ||||||||||
| 中四国ブロックでは年に2回にわけて研修会をしています。エイズ拠点病院数が58で、一度に全部は無理だからです。2000年度までの参加者数は、のべ164人でした。具体的なスケジュールは表をご覧ください。医師による「HIV感染症の病態と治療」についての講義。薬剤師による「抗HIV薬の特徴」についての解説。HIV感染者の体験談。心理専門家による「服薬援助に関連したコミュニケーションの考え方」の解説。事例検討。そして、ロールプレイによる実習です。 | ||||||||||
| ● 薬剤師のコミュニケーション技法の特徴 | ||||||||||
| ロールプレイ場面を録画して後から解析しました。薬剤師のコミュニケーションを技法に注目しますと、次のような点が指摘できます。 | ||||||||||
|
||||||||||
| ● 初参加者と経験者には差がある | ||||||||||
| この研修会は、一つの施設からはなるべく同じ薬剤師に参加してもらって、ステップアップを図りたいと思っています。それでも施設の都合で、新しい方が参加することもあります。2000年度は半数以上が研修経験者(リーピーター)でしたのでビデオ記録から、初参加者とリピーターを比べました。 | ||||||||||
| リピーターは、視線を合わせて、相づちをうちながら患者の話を聞き、服薬にまつわる不安に配慮していました。応答には相手の言葉を反復することにより、発言を受けとめたことや理解を伝え返しました。患者の質問にすぐに答えを与えようと焦らず、一つの話題に時間をかけて話し合いました。研修を重ねると、これらの技法の使用が増えることがわかりました。 | ||||||||||
| ● 研修会参加前後のアンケート比較 | ||||||||||
| 参加者からは研修会開始前と終了直後に、アンケートで同じ項目を質問しました。つまり「この研修会で、何を期待されていますか?」に対し、「この研修会で何を得ることができましたか?」というものです。期待と達成では「知識の獲得」が最も多く、次いで「コミュニケーション技術の獲得」、「具体的な関わり方」、「患者さんとの交流」などが評価されていました。 | ||||||||||
| 研修会のスタッフには心理職・ソーシャルワーカー(MSW)が医師とともに加わっており、ロールプレイでは模擬患者を演じました。多くの医療施設では、薬剤師と心理やMSWは日頃つきあうことが少ない職種同士でしたが、貴重な交流経験だったという感想がありました。 | ||||||||||
| 4.HIV治療チームの中での薬剤師の役割 | ||||||||||
| ● 服薬援助の知識と技術を深めること | ||||||||||
| 薬剤師は、薬理学についての自分のスペシャリティには自信と責任を持って対応しています。症状や薬の作用、副作用、服薬行動といったことに焦点づけが集中しています。しかし今後は、さらに患者自身やその生活の中身にも焦点を当てて理解していくことが望まれます。 | ||||||||||
| 特に患者の服薬動機づけを高めるためには、薬剤師の側から患者の心理的理解を深めることができるようになる必要があります。服薬がきちんとできない患者の心理社会的問題に気づくことが大切で、問題解決のために看護職、心理カウンセラー、さらにソーシャルワーカーなどの援助チームの一員になることが必要でしょう。 | ||||||||||
| 施設の実情によって違いますが、薬局の中でHIV感染症や抗HIV薬についての勉強会の中心になることも望ましいことです。HIV感染者を抱えている医療機関では、定期的に医師・看護職・心理職・福祉職そして薬剤師が合同でカンファレンスを持って、新しい情報の交換や事例検討を行い、良いケアのための知恵と工夫を重ねることが大切です。 | ||||||||||
| 5.最後に | ||||||||||
| 研修会で夜遅くまで、他の病院の薬剤師と語り合いました。抗HIV薬は専門性が高く経験の交流も大切です。それぞれの薬局に核となる薬剤師が育ち、知識の伝達と技術の向上をはかり、また他施設とのネットワークが形成されていくことが望まれます。この研修事業を通じて、中四国地方のHIV感染者に、より質の高いケアサービスが提供できるようになることを希望しています。 | ||||||||||
| これまでの研修会で講演して頂きました、山元泰之(敬称略、東京医大臨床病理)、日笠 聡(兵庫医大第二内科)、今村顕史(駒込病院感染症科)、桒原 健(国立大阪病院薬剤科)の他、多くの講師のみなさん、患者さん、スタッフの広島県臨床心理士会、広大病院薬剤部・エイズ医療対策室のみなさんにお礼を申し上げます。[End] |