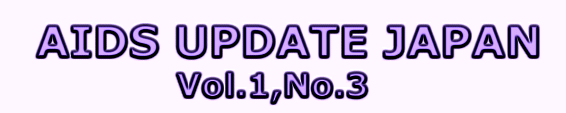 |
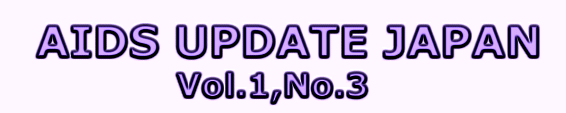 |
|
|
|
|
| ■ 「HIV感染症に関する臨床研究班」(木村班)は今年度が3年目で、区切りの年に当たります。この班はHIV感染症に関連して生じて来る日和見感染症の早期診断法や治療法の検討・開発とか、HIV感染症の治療法の検討・開発などを主たる目的としています。目下3年間の研究成果につき各班員に報告書をもとめてもらっている最中で、まだ3年目の報告が届いていない段階ですが、2年目までにも既に多くの有益な成果が得られていますので、その一部を紹介します。日常のHIV診療に役立てて頂けると幸いです。 | |
| 1.日和見感染症の全国調査 | |
| ■ HIV感染症にみられる日和見感染症に対する対策を立てるには、先ずその実態を知る必要があります。また、その実態は国により大きく異なるので、海外のdataはあてにならず、日本独自のdataが必要ですが、これまで日本全体の成績はありませんでした。そこで全国の拠点病院の協力のもとに1996年と1997年に経験したエイズ指標疾患を調査し、約1,000例の報告を頂きました。1位がカリニ肺炎(27%)で、以下カンジダ症(16%)、サイトメガロウイルス感染症(14%)、結核(9%)、非定型抗酸菌症(6%)の順でありました。この実態は他のアジア諸国のものと大きく異なっています。カリニ肺炎の場合発症の時期もCD4陽性リンパ球数でみると、今迄言われていたよりも遅く、一部の例外的症例を除き100個/μL以下であり、日本の場合発症予防投与開始時期を従来の200個/μLから100個/μLに切り下げても良いのではないかと思われます。 | |
| 2.針刺し事故の全国調査 | |
| ■ 欧米では針刺しなどの汚染事故で既に300名近い医療従事者がHIVに感染したことが確実、ないし疑い濃厚とされています。幸い日本では医療従事者が針刺し事故で感染した事例はありませんが、そのような事が起こると多くの医療機関が警戒し、患者さんの受け入れ体制が大きく後退してしまう虞れがあります。針刺し事故は患者さんのためにも、医療従事者のためにも是非とも防止しなくてはなりません。 | |
| ■ そこで、事故防止対策策定の参考にするため、これも全国の拠点病院にお願いし、事故情況の調査をさせて頂きました。過去2年間で約10,000例の事故報告を頂きました。もちろんこれは感染症の有無にかかわらず、全ての事故についての報告ですが、日本で最大規模の集計です。その結果は既に一昨年と昨年の報告書に載っていますが、依然としてリキャップ時の事故と翼状針による事故が多く、アメリカの情況と大きく異なっています。アメリカではリキャップ禁止が徹底され、またリキャップ不要な安全装置付きのものが多用されているためであります。アメリカでは州法により安全器材を使用するよう全ての医療機関に義務づける州が増えており、近々そのような州が20州を越える見込みで、日本も見習うべきでありましょう。 | |
| 3.日和見感染症のPCR診断 | |
| ■ 日和見感染症の制御には早期診断、早期治療が決め手となります。PCR診断は早期診断に適しているうえ、治療効果の判定にも威力を発揮します。当研究班の複数の班員は、これまでにpneumocystis carinii、Mycobacterium tuberculosis、Aspergillus、Toxoplasma gondii、cytomegalovirus、JC virus、EB virusなどに対するPCR系を確立し、早期診断と治療効果モニターに活用しています。特に鑑別診断が難しい脳病変のトキソプラズマ脳炎、脳原発リンパ腫、進行性多巣性白質脳症(PML)につき、それぞれT. gondii、EB virus、JC virusをターゲットとし、髄液でPCRを行い、各85~100%の確率で診断できる系を確立できました。 | |
| 4.日和見感染症診断検査法の講習会 | |
| ■ HIV感染症/エイズにみられる原虫症や寄生虫感染症には稀なものが多く、通常の診療の中ではなかなか遭遇することがなく、検査部における検出能力、診断能力に不安があります。そこで当研究班では毎年2回ずつ拠点病院の検査技師を対象に、1病院から1名を限度とし希望を募り、実習主体の講習会を実施しました。各回80名前後の出席があり計300名以上が参加し、大変好評でした。赤痢アメーバ、トキソプラズマ、クリプトスポリジウム、ニューモシスチスカリニを中心に形態学や染色法、検出法の講習を行いました。今年度も実施し、日本における原虫症などの診断能力向上のために努力する所存です。 | |
| 5.日和見感染症の予知・予防に関する研究 | |
| ■ 精度の高い定量的PCRを用いることにより、血清中サイトメガロウイルス(CMV)などの日和見感染症の病原体を定量的に測定する方法を樹立しました。この方法により、多数例につき検討した結果、血清中CMV量が一定濃度を越えるとCMV感染症が発症することがつきとめられました。これまではCMV感染症の発症予防の指標にはCD4陽性リンパ球数が用いられ、50個/μL以下となったらガンシクロビルを予防的に経口投与する方法が標準的方法となっていますが、これでは無駄な投与が多いことが問題となっていました。これに対し、血中CMV量を指標とすることにより、より正確に発症が予知でき無駄のない予防ができることになると思います。 | |
| 6.日和見感染症に関するその他の検討 | |
| ■ 赤痢アメーバやトキソプラズマの新しい検出法や血清診断法を確立し、またそれらの新しい治療ターゲットを見い出しました。カリニ肺炎の新しい治療法を検討しています。クリプトコックス症のCNSへの播種のメカニズムを解明し、播種予防の検討を行っています。その他、難治性肺結核のサイトカイン、リンホカインを併用した治療法など多数の研究が続けられています。 | |
| 7.至適抗HIV治療法を見い出すための検討 | |
| ■ 日本でも3剤併用による強力な抗HIV療法(HAART)が可能になりましたが、日本人にとってどの組み合わせが飲みやすく効果的なのかなどが全く不明です。そこで当研究班では、全国で行われている治療法を集計し、その治療成績や副作用の具合、コンプライアンスの状況を検討しています。最初の2年間は症例の集積にあて、今年度、その成績を解析し報告することにしております。これがまとまると、どの組み合わせが好ましいかにつきより具体的なガイドラインが作れるものと期待しています。 | |
| 8.HIVの薬剤耐性変異検査の有用性に関する研究 | |
| ■ HAARTで治療した場合、いつ頃から耐性ウイルスが生じて来るのか、また、耐性ウイルスが生じた場合その治療はいつまで続けられるのかなど、基本的な点がまだ明らかでありません。これまでに130名余りのHAART療法中の患者さんのHIVを調べた範囲では、約60%の患者さんでは治療開始後3ヵ月以内に血漿中HIVが103コピー/mL未満となり、その時点でも、またその後も耐性ウイルスの出現はみられません。一方、3ヵ月後に血漿中HIVが104コピー/mL以上の患者さんは20%弱で、これらの患者さんでは9ヵ月後までに全員が耐性ウイルスを持つようになり、CD4陽性リンパ球数も徐々に低下しました。 | |
| ■ このような結果から、HAART開始後3ヵ月目の血漿中ウイルス量が103未満の群では耐性ウイルスは当面出現しないので、その治療を安心して続けられること、104以上の群では全員耐性化するので、早目に治療薬を変更するべきであること、中間的HIV量を示した群では耐性変異検査を行いつつ治療を続け、耐性ウイルスが出現して来たら他剤に変更すべきであること、などが明確に示されました。 | |
| 9.新規抗HIV薬の開発 | |
| ■ 核酸系アナログの逆転写酵素阻害活性をスクリーニングした結果、F-ddAが有望であることを見い出しました。この物質は耐酸性であることから胃酸で分解されることもなく、吸収率も高いです。さらに耐性ウイルスができても、その耐性度が軽度であり、他の核酸系逆転写酵素阻害薬との間に交差耐性が認められない、など多くの利点を持った薬剤と考えられます。このような長所が注目され、現在アメリカで臨床試験が行われています。さらにはCCR-5-binding domain mimicをデザインし、CCR-5との結合阻害薬を開発する研究も進められています。 | |
| 10.HIV感染症の病態解明に関する研究 | |
| ■ HIV感染者の体内ではHIVに感染したCD4陽性リンパ球のみならず未感染のCD4陽性リンパ球もアポトーシスにより破壊されています。そのメカニズムをFas抗原の発現との関連を中心に検討しています。アポトーシス防止法発見の手掛かりとなればと期待されています。また、IL-15が濃度依存的にHIV感染細胞のアポトーシスを抑制すること、これがFas/Fas-リガンドの制御によることを見い出しました。治療に応用することを考えています。HIV感染症による免疫不全はHHV-8の複製を許し、このことがカポジ肉腫の発生に関与していると推定されていますが、このHHV-8由来のvIL-6はHIVの複製を促進すると言う悪循環を形成していることを見い出しました。またvIL-6はhuIL-6の産生を促進し、カポジ肉腫、キャスルマン病、リンパ腫などを起こしていることが示唆されました。 | |
| 11.男性HIV感染者における配偶者間人工授精に関する研究 | |
| ■ 性行為によるHIVの伝播が主要な感染経路となっている本疾患においては、感染予防と挙児希望を共に満たすことはなかなか困難といえます。しかし、HAARTの進歩に伴い挙児を希望する患者さんが増えていることから、精液よりHIVを除去し、妊孕性のある精子を選別する方法を種々試みています。現在のところ、swim-up法、密度勾配法などによりHIV量を大幅に減少させることには成功していますが、完全に除去することはできず、更に改良を進めています。 | |
| ■ 以上、木村班の主な活動につき述べました。これ以外にも、多くの研究が熱心に進められています。いずれも臨床に密着した大切な研究ですが書ききれませんでした。HIV感染症の臨床研究はHIVを知っているだけでは無理で、広く感染症全体を知らなければできません。その意味で木村班にはHIVの専門家の他に、感染症の専門家にも加わってもらって協同研究を進めて来ました。これにより、HIV感染症の研究の輪が、大分広がって来たように思います。今年度はこれらの成果を臨床に役立てる形でまとめたいと思っています。 |
|
|
|
|
| ◆ HIV感染症の疫学研究の目的 | |
| ■ HIV感染症の疫学研究の目的を一言で言えば、「HIVの予防に、間接的あるいは直接的に役立つevidenceを得ること」ということになります。そのために、疫学研究班では、HIVの流行状況(サーベイランスデータの解析を含む)、リスク行動のまん延状況の把握、推計・将来予測、有効な予防対策モデルの開発といった研究を行っています。 | |
| ◆ 研究の困難 | |
| ■ しかし、言うほど研究は簡単ではありません。エイズの疫学には、他の疾病の疫学には見られない困難が伴うからです。最大の問題は、性のタブー視、男性同性愛者への差別、薬物使用・売春・(外国人の)オーバーステイ等の非合法性といった社会的問題が、必要な対象者へのアクセスを困難にしていることです。エイズの疫学では、喜んで研究の対象になってくれる人などはいません。研究者の「権威」は無力であり、時間をかけてHIVの影響を受けやすい人々とのパートナーシップを築かなければ、一歩も前に進むことができないのです。もうひとつの問題は、エイズの疫学には、社会科学的研究が不可欠ですが、日本の疫学は、伝統的に社会科学とのinteractionが乏しく、構造的にその部分がほとんど欠落してきたことです。その部分については、ほとんど一から始めることを余儀なくされてきました。また、「公衆衛生学者」がこぞって慢性疾患に頭を向けている中、この時期におけるエイズ疫学研究の意義を理解する研究者が少ないのも研究を困難にしている原因のひとつと言えるでしょう。 | |
| ◆ 疫学研究で得られた成績の概要 | |
| ■ しかし、こうした中でも、少しずつ、情報の蓄積が進み、次第に「日本のエイズ」の実像とその方向が明らかになりつつあります。その特徴をまとめると、①依然流行レベルは低いが、近年流行が加速した、②流行には欧米性とアジア性が混在するという2面性があり、流行拡大のポテンシャルは、同性間感染及び異性間感染いずれもかなり高い、ということになると思われます。 | |
| ■ 我々の予測によれば、1998年時点の感染者数は約8,000人で、2003年には約16,000人に増加します。年に1,600人増加する勘定ですが、このペースは研究班が以前に行った予測を超えるものであり、流行が最近加速したことを示唆しています。増加は、日本人男性、特に若い世代における国内感染の増加がその中心です。感染経路としては、同性間感染と異性間感染がほぼ同数で増加しており、これは、同性間感染が圧倒的に多い欧米と、異性間感染が圧倒的に多いアジアとの中間的な特徴を持つことを示しています。同性間感染については、感染率の調査からも、確かに男性同性愛者間に感染が拡大している証拠が得られており、また、異性間感染については、1994年以降HIV-1のサブタイプEが優勢になったことが明らかとなり、東南アジア系外国人女性から日本人男性への感染が生じた可能性が示唆されています。また、本年実施された性行動調査の結果も、欧米流に若年者での性の自由化がおおいに進んだことを示す反面、男性で過去1年に買春を経験した人が10%にも上る(欧米はせいぜい数%)など、アジア的な性行動の特徴を有することを示唆しています。 | |
| ■ このように、わが国の流行の規模と予測と流行の特徴のアウトラインを明らかにし、日本のエイズ流行を捉える視点を定めることができたことは、疫学研究班の重要な貢献であると考えられます。 | |
| ◆ エイズ疫学研究の「構造改革」 | |
| ■ しかし、日本のエイズの疫学は、まだ発展途上であり、確固たる体系に至るまでには、もう少し時間がかかるように思われます。エイズの疫学研究には、目指すべき方向があります。それは初めに述べた、「HIVの予防に、間接的あるいは直接的に役立つevidenceを得る」ために必要な体制を整えるということです。しかし、その方向は従来の「公衆衛生学的」疫学研究の延長上にはなく、むしろ、それとは違う方向に存在しています。実は、この数年間は、そのために研究班として「構造改革」を企てた時期であり、幸いなことに、その方向に向かって少し前進することができました。 | |
| ■ この間実現してきたことを上げれば、まず第一に、研究班の中に、ゲイ、セックスワーカー、薬物使用経験者、外国国籍者などの幅広いNGOの参加を得ることができたことが上げられます。いわゆる研究者の守備範囲など所詮狭いものです。NGOがよき研究のパートナーとなることによって、研究のウイングを拡げ、リーチを深めることができます。第二には、これまで日本では不可能と考えられてきた性行動調査を成功させることができたことがあげられます。昨年から本年度にかけて、無作為抽出された国民、全国国立大学生、全国のSTD患者の性行動調査を、様々な問題を克服して次々に実施してきました。先述した日本人の性行動の特徴はその成果の一部ですが、その他にも日本人や学生の性行動の特徴や知識レベルについて、予防に役立つ重要な情報が得られる見込みです。第三には、非確率サンプリング、マーケティング、準実験的疫学研究(Quasi-experimentation)という社会科学的手法による予防介入研究の実施に踏み切ったことがあげられます。このタイプの研究は、プラクティカルで予防に直接結びつくものであり、今後のHIV感染症の疫学研究の中で大きなウェイト占めていくことになります。 | |
| ◆ 最後に | |
| ■ こうして、HIV感染症の疫学研究は、限られた範囲とは言え、成果を上げ、また新しい研究体系へと進んできました。しかし、いつも私の頭の中には、研究は果たして間に合うのかという焦燥感のようなものがあります。流行は加速しているようであり、研究もそれに負けないように質を高めつつペースを上げなくてはなりません。他の国では、流行の拡大後に、研究が成熟したという皮肉な歴史がありますが、我々は、流行が拡大する前に研究を成熟させ、流行の抑制に貢献したいと思います。いつも、講演などの折りに強調することですが、このままでは日本の流行は、同性間感染等による流行である第1波を経て、異性間感染による第2波へと移行していくことになります。第2波は非常に大きなうねりを持つ波になると考えられていますが、どれほどの波になるかは、どれだけ早期に有効な対策を講じることができるかかかっています。 | |
| ■ 流行を防止するのに役立つ疫学研究。微力な我々にとって、これは大それた希望かも知れませんが、西暦2000年という何か大げさな年の年頭の抱負として掲げておきたいと思います。 |
|
|
|
|
| ■ 「班会議があるのですが、これからの外国人患者に対するAIDS医療体制の確立にひとはだ脱ぐつもりで、来て貰えませんか。」吉崎先生から突然の電話がかかってきたのは、たしか1998年の梅雨明けの頃だった。以前から、うちの附属診療所では、HIV感染者の方の診療もしていて、ポルトガル語、タイ語、英語の方の対応もした。患者さんの片言の日本語、難しい言葉を使わないで説明する医師、でもタイ語の時は、最初の頃は通訳の方に来ていただいた。診察室は患者、医師、看護婦、カウンセラー、通訳、そして仲立ちをした私という調子であった。医師も検査、薬、金額を気にしながら指示を出して、看護婦が素早く電卓で計算して、「大丈夫? 払える?」と聞くという調子の診察風景があった。対訳の印刷物もあればもっと助かると思って、近畿エイズ学会でお会いした吉崎先生に聞いたのだが、その時は「そんなのはない」との答えだった。 | |
| ■ 班会議に出ていくと東海ブロックの方では、ポルトガル語の対訳服薬マニュアルを作ったとのこと、在日外国人への対応に苦労されているとの事だった。従って私は対訳の服薬説明書や資料を作ればいいのかなと思った。 | |
| ■ 京都のYWCAで外国人支援の活動をしていた榎本さん、青木さん、以前から性教育の世界で共に活動してきたプレイス東京の池上さんや風俗産業に働くタイ人女性の調査の研究をしていたニクンさん(タイ語)に協力を求めた。またエイズ予防財団の友人を通じて、岩木さん(ポルトガル語)、さらに栄口さん(スペイン語)、さらに中国語は三冬社を紹介してもらった。9月から12月にかけて、これらの人と会い、お願いをし、各国の状況を聞いて回った。翻訳をお願いした人は、HIVや医療の言葉のわかる人を探した。なにしろ、英語すら心もとない私に言葉などチェックできない。ここは実績のある信頼できる人を探すしかないというわけである。 | |
| ■ その頃、榎本さんが、大阪での経験から、病院のシステムや医療のことをもっと通訳に知ってもらわないとと言う。対訳資料を作るよりこちらが先だと。そこで、通訳の為のセミナーを企画し、1999年の末に京都で通訳養成セミナーを開いた。このセミナーを開く過程で芋づる式に、沢田、鬼塚さん等たくさんのNGOで活動している人たちを知った。このセミナーはとても勉強になった。生意気にも、「HIV/AIDS患者支援通訳養成講座」と題を付けてしまったが、これはまさに研究の場、問題点掘り起こしの場となった。12日の泊り込みセミナーは、通訳と医療者のひざをつき合わせての議論が夜が更けるまで続いた。国による違いも多少はあるが、通訳の方が燃え尽きそうになって、言葉の問題、制度の壁、経済的問題と格闘している姿も見えてきた。 | |
| ■ 一方対訳マニュアルも順次出来てきた。最初はそのままレイアウトだけ統一して、コピー配布の予定であったが、印刷費用の目途が立ち、出版社にお願いすることとなった。タイ語は対訳すると1.5倍のボリュームになる。でも字のポイントを落とすと読みにくくなる。吉崎先生はこだわってレイアウトに工夫をこらした。また、タイとロシア語圏では午前・午後という時間の分け方の概念はないこと。この二つについては慌てて、24時間表記に変えた。さらに、1日3回、4錠服用という表現も、英語や仏語、ポルトガル語、スペイン語にするとTake 4 tablets, 3 times a day.となる。これでは間違いやすいと、日本語の方を1日4錠づつ3回服用という表記に変えた。言語の特性、文化の違いまでも配慮しなければならないことを勉強した。タイ語の校正は4回を数えた。 | |
| ■ 予備的にタイ語の服薬指導書をタイ人患者に見せた時の彼女の笑顔を私は忘れることが出来ない。それまでの診察室での緊張感が一瞬ほぐれた。医療者の方から歩み寄ろうという姿勢、これこそが患者と接するときに必要なのだと思った。対訳服薬指導書も完成されたものではない。内容的にもすでに古いとの声もある。でも、診察室で患者と医療者の歩みよりのツールには十分使えるはずである。対訳資料が、患者への歩みよりの第一歩として活用頂けることを願うしだいである。在日外国人患者を取り巻く状況の厳しさが、この一年、やっと私にも見えてきた。改善できるとこらから、少しずつ取り組むことが出来ればと願うしだいである。 |
|
|
|
|
|
|
|
| ■ 最近HIV-1の化学療法の分野では、2剤のヌクレオシド型逆転写酵素阻害剤(NRTI)と1剤のプロテアーゼ阻害剤(PI)、あるいは2剤のNRTIと1剤の非ヌクレオシド型逆転写酵素阻害剤(NNRTI)を中心とした多剤併用療法が適用されるようになり、感染者体内のHIV-1の増殖をほぼ完全に押さえ込み、病気の進行を抑えることが可能となりました。そしてウイルス増殖を押さえ込むことに成功した症例では、減少していた抹消血中のCD4数が正常値までに回復することも期待できるようになりました。この多剤併用療法の導入により、米国においてエイズによる死亡率が減少したことは記憶に新しいことと思います。 | |
| ■ しかし残念なことに多剤併用療法を受けながらも効果が十分にあがらず、ウイルスの増殖抑制に失敗する症例も数多く出現しました。失敗の理由としては、不十分な服薬、薬剤の吸収障害そして生体内薬物代謝障害などのために、治療薬剤の血中濃度がHIV-1増殖を押さえ込むことができるレベルまで達しない、そして維持できないことがあげられます。 | |
|
|
|
| ■ HIV-1の逆転写酵素は逆転写精度が低いことが知られています。遺伝子が突然変異を起こす頻度は、複製サイクル一回毎に3×10<-5>個と考えられています。さらにHIV-1は生体内において極めて活発に増殖することが知られており、生体内で新たに生み出される変異体は一日あたり10<9-10>個になると考えられております。したがって単純計算で一日に10<9-10>個のウイルスが1回の複製を行なったとすると、少なくとも1個の塩基置換を伴ったウイルスが3×10<4-5>個生じることになります。このようにして生み出された変異を持ったウイルス種族は、さらに宿主免疫などによる選択を受け、極めて多様性に富み、刻々と変化する集属を形成していきます。このように均一でない、そして不安定なHIV-1集属は治療薬剤が至適濃度以下で存在する状況下では、複製を繰り返し、薬剤に対して耐性変異をもつウイルスが容易に選択されていきます。さらに生き残ったウイルスをもとに、より薬剤に対して抵抗性を持つ変異体が選択され、このステップが繰り返されることにより、時間とともに薬剤耐性に関連した変異ウイルスが集積し、薬剤耐性のレベルが上昇していくと考えられます。 | |
| ■ 理論的に全く薬剤を投与されていない状況下でも、偶然ある種の薬剤に対して耐性を持つようなウイルスが存在するのかもしれません。ただし多くの場合、薬剤耐性をもつウイルスは持たないウイルスに比べて増殖能、適合性が低いために、薬剤が存在しないかぎりは宿主体内で優位の集属として生き残ることは困難と考えられます。 | |
|
|
|
| ■ 一般的に薬剤耐性ウイルスの出現は、患者の病気の進展を速めると考えられています。しかしながら薬剤耐性変異が検出されたこと自体は、治療薬剤の完全な無効を意味するものではありません。したがって治療に使用している薬剤に対して耐性変異が検出されたからといって、直ぐに薬剤の変更が必要というわけではありません。その時の血中ウイルスRNAコピー数、末梢血中CD4数によりその意味合いが変わってきますので、総合的に薬剤の効果を評価をする必要があります。現時点では治療薬剤の変更時期の決定は、基本的にはウイルスコピー数の変化をみて行うべきであり、次にどの薬剤に変更すべきか判定するために薬剤耐性を用いることが妥当と考えられます。 | |
|
|
|
| ■ 薬剤耐性を獲得したHIV-1を検出するには、(1)ウイルスの変異を遺伝子レベルで検出する遺伝子型解析と、(2)ウイルスを患者血中より分離して薬剤に対する感受性を直接調べる表現型解析の二つの方法があります。それぞれ長所と短所があり、得られる結果も質的に異なるものです。現在普及しつつあるものは遺伝子型解析であり、一部の機関では表現型解析も行われつつあります。 | |
| ■ では薬剤耐性検査は治療を進めるうえで役に立つのでしょうか。最近、欧米において遺伝子解析による薬剤耐性検査の治療を進める上での有用性についての調査が行われました(Viradapt study)。この調査では治療を進めるとき遺伝子解析検査を行っていた患者群と、行っていなかった患者群の2群について、治療の効果を血中ウイルスRNAコピー数で評価を行いました。その結果、遺伝子解析検査を行いながら治療を進めていた患者群のほうが、血中ウイルスRNAコピー数をより低い状態に押さえ込むことができたという結論が出ています。この調査が示すように、薬剤耐性遺伝子検査は治療を進めるうえで有効な指標と思われます。一方、薬剤感受性検査に関しても類似の調査が行われつつあり、同様にその有効性が期待されています。 | |
|
|
|
|
■ 私たち国立感染症研究所エイズ研究センターでは、1996年より各地の医療機関と協力してHIV-1薬剤耐性検査を実施して来ました。私たちは特に長期間の追跡調査を主眼に検査を行っており、ヒト体内での薬剤耐性ウイルスの選択、進化がどのように進んでいくのか、臨床経過と治療プロトコールとの関連、そしてどのようにしたら薬剤耐性ウイルスの出現を最小に押さえ込むことができるか、薬剤耐性の機序の解明を目指して研究を進めております。今後とも皆さまのご理解とご支援をお願いいたします。
|
|
|
|
|
|
|
|
| ■ 1999年末の時点で、世界には3,360万人がHIVに感染、あるいはエイズ発病していると推定される。そのうち3,240万人が大人で、120万人が15才未満の子供である。69%以上にあたる2,330万人はサハラ以南のアフリカに住んでおり、18%つまり600万人が南アジアと東南アジアである*1)。 | |
| ■ 世界的には、15才から49才の成人のおよそ100人に1人はHIVに感染している。サハラ以南のアフリカでは、この年代の成人の8%が感染している。アフリカ諸国の中には15才から49才の成人人口の20%以上に達している国もある*1)。 | |
| ■ 世界でHIV/AIDSで生存中の成人3,240万人のうちのおよそ46%は女性である*1)。 | |
| ■ 1999年には世界で560万人が新たにHIVに感染したと推定される*1)。これは1日あたり15,000人を越える。新規感染の95%は開発途上国で発生している*1)。 | |
| ■ 1999年には、毎日7,500人におよぶ15才から24才の若者がHIVに感染した。これは5分に1人の割合である*1)。 | |
| ■ 1999年までに、世界でHIV感染症あるいはエイズに関連した死亡者数の累計は、およそ1,630万人で、1,270万人が成人、360万人が15才未満の子供であった*1)。 | |
| ■ 1999年だけでは、HIV感染症あるいはエイズに関連した死亡者数は世界で260万人であり、15才未満の子供47万人が含まれている*1)。 | |
| ■ 世界では、成人のHIV感染者の80%以上が異性間の性行為による感染である*1,2)。 | |
| ■ 世界の子供や新生児のHIV感染の90%以上の原因は、母から子供への(垂直)感染である*1,2)。 | |
|
|
|
| ■ 米国疾病予防管理センター(CDC)では、アメリカに在住するHIV感染者数は65万人から90万人の間であり、このうち20万人は自分が感染していることに気がついていないと推定している*3,4)。 | |
| ■ 1998年にはアメリカではおよそ4万人の新規HIV感染が発生し、70%が男性、30%が女性と推定される。この新規感染者の半数が25才未満である*5)。 | |
| ■ CDCは、アメリカの男性の新規感染者のうち、およそ60%が同性間の性行為によって、25%は静脈注射使用によって、15%は異性間の性行為によって感染したと推定している。新規感染の男性のうち50%が黒人で、30%が白人、20%がヒスパニック系であり、他の民族・エスニック群の占める割合は少ない*5)。 | |
| ■ CDCは、アメリカの女性の新規感染者のうち、およそ75%は異性間の性行為によって、そして25%が静脈注射使用によって感染したと推定している。これら新規感染の女性の中で、64%が黒人、18%が白人、18%がヒスパニック系であり、他の民族・エスニック群の占める割合は少ない*5)。 | |
| ■ アメリカでは1999年6月30日までに、合計711,344人のエイズ発病者がCDCに報告された*6)。 | |
| ■ アメリカで新規のエイズ発病と診断される患者数は、1996年から1997年にかけて18%(実数では60,434人から49,690人に)減少した。1997年から1998年にかけては、44,307人であり11%の減少であった*6)。 | |
| ■ アメリカの小児エイズ患者の年間発生数は、1992年の949人から1998年の225人へと減少した*6)。 | |
| ■ 1985年から1998年にかけて、アメリカのエイズ患者に占める女性の割合は、7%から23%にまで増加した*6)。 | |
| ■ 1998年におけるアメリカの新規エイズ患者数の比率を人口10万人あたりでみると、黒人では81.9人、ヒスパニック系では34.7人、白人では8.4人、アメリカ・アラスカ先住民では9.4人、アジア太平洋系では4.1人であった*5)。 | |
| ■ 1998年末には、アメリカには297,137人のエイズ発病患者が生存中であり、1997年に比べると10%増加していた*6)。 | |
| ■ 1999年6月30日の時点では、CDCに報告されたエイズ患者の死亡者数は420,201人であった*6)。アメリカでは25才から44才までの人の死亡原因のうち、不慮の事故、癌、心疾患、自殺に次いで第5位となっている*7)。 | |
| ■ 1996年にはアメリカでは37,221人のエイズ関連死亡が発生した。1997年には21,445人で、42%低下した。1998年には17,171人となって前年より20%減少した*6)。 | |
| ■ 1998年のアメリカのエイズ死亡者の率を人口10万人あたりでみると、黒人では32.5人、ヒスパニック系が12.2人、白人が3.3人、アメリカ・アラスカ先住民が4.2人、アジア太平洋系が1.3人であった*5)。 | |
|
【参考文献】 1) UNAIDS: AIDS epidemic
update: December 1999. |
|
|
|
|
|
|
|
| ■ 厚生省のエイズ動向委員会(柳川 洋委員長)が11月30日にまとめた2か月間のエイズ患者・感染者情報(8月30日から10月31日)によると、患者50人、感染者76人であった。前回2か月間(6月28日~8月29日)の報告数に比べ、感染者数は10人減り、患者数は1人増えた。感染者数の減少はすべて外国人で、日本人は前回と66人と変化がない同数だった。 | |
| ■ 今回は女性感染者15人のうち、12人が10歳代(2人)と20歳代(10人)の感染であった。委員会は、異性間の性的接触で10歳代の女性で2人の感染例が出たことを重視し、若い女性に報告が集中する傾向がみられると分析している。 | |
| ■ 同委員会が30日まとめた今年上半期(6月27日まで)の新たに報告されたエイズウイルス感染者は230人、エイズ患者は145人で、患者数は過去最高だった。感染者数も230人で、保健所の無料検査実施で外国人女性の報告数が急増した1992年下半期に次ぎ過去2番目となった。 | |
| ■ 感染者230人のうち、異性間の性行為によって感染した人が84人、男性同士の性行為が88人を占めている。患者145人中では、異性間の性行為82人、男性同士の性行為は21人だった。 | |
| ■ 感染者のうち日本人は179人(男161人、女18人)、外国人は51人(男21人、女30人)であった。男性のHIV感染者の増加は、性的接触による感染が中心で、20代の異性間の性的接触と、20~30代の同性間の性的接触による感染が増えている。女性は異性間の性的接触による感染が中心で、特に20代の感染が大幅に増加している。 | |
| ■ 地域的には、関東・甲信越地方、東京都での感染者の増加が著しいが、近畿地方でも増えているとのこと。(鴨 愼一) | |
|
|
|
|
|
| ■ 第13回日本エイズ学会学術集会・総会が1999年12月1日から3日まで、東京都北区王子の「北とぴあ」で開催されました。総会長は東京都立駒込病院感染症科の根岸昌功先生でした。駒込病院は日本で最初に「エイズを診る」と公言し、実際に多数の患者の診療にあたってきました。今回は企画や運営にボランティアたちが加わっているようで、会場入り口では総会オリジナルTシャツが販売されていました。 | |
| ■ エイズに対する一般の関心が薄れ、メディアの取材も非常に減っています。しかし事務局の話によると、参加者数は予想を上回りおよそ1,000人だったそうです。一番困ったのは、非学会員で当日参加をした多くの人たちには、プログラム・抄録集が部数不足でまわらなかったことです。今回から抄録集は定期刊行物である学会誌に組み入れられ、事前に配布されたためです。改善が望まれます。 | |
| ■ この学会の最も大きな特徴は、参加者の背景や職種が実に多様であるということでしょう。それぞれ何人かはわかりませんが、臨床医、看護婦・看護士、基礎医学・薬学・製薬企業の研究者・学術担当者、検査技師、薬剤師、心理職、医療ソーシャルワーカー、教育関係者、行政、患者・ボランティアまで実にさまざまです。まさに「エイズ医学会」ではなく「エイズ学会」です。 | |
| ■ 1987年に第1回が京都で開催された時は、エイズ研究会という名前で、2会場2日間でした。しかし、今回は4会場3日間で270の一般演題(口演とポスター)、4つのシンポジウム、3つのセミナー、4つのセッション、1つの特別教育セッションという内容でした。演題数が増え、大きくなるのはいいことですが、聞きたい内容が別会場で聞けないのは残念です。 | |
| ■ 特別教育セッションは、エイズ治療研究開発センターの青木 眞先生の司会で行われました。元はアメリカの教育システムです。模擬患者の病歴やデータがスライドに写り、治療の選択肢が複数提示されます。会場前方に日本の医師50名が無線のリモコンのようなものを持って座っています。回答をすると直ちに集計結果が、液晶プロジェクターによってスクリーンに映し出されます。みんな一致するものもあり、ばらつくものもあります。間違えて答えても恥をかくことはありません。問題を出したスクーリー教授とベンソン教授が、掛け合いで回答とコメントをつけていきます。日本の医師達も、よく考え抜いた答を出していました。学会の教育セッションとして、このように会場全体で楽しみながら参加する形式は、非常に評判がよいものでした。 | |
| ■ ショックだったのは東京都衛研と横浜市衛研の発表。日本でも薬剤耐性HIVの感染例が出たと言うものです。東京都衛研の貞升健志さんらは、東京都内の保健所と南新宿検査相談室で最近HIV抗体検査が陽性であった44例の遺伝子解析を行ったところ、4例で複数の逆転写酵素領域の変異がみられ、AZTや3TC耐性型であったというものです。横浜の例は、急性感染症状で診断された患者で、同様の耐性変異がみられたというものです。詳細は不明ですが、薬を飲んでいる人からの感染と思われ考え込んでしまいました。 | |
| ■ さて、抄録集に「・・・の検討を行う」として、結果が記されていない見込み抄録は見苦しいものです。また抄録と発表の内容がまるきり違うというのも、抄録集の価値を下げます。今後は海外の学会のように、演題締め切りを過ぎたものでも、優れた発表は受け付けるという「Late Breaker」制度を作ってはいかがでしょうか。 | |
| ■ この総会は初めて本格的なホームページを公開しました[ http://www.lapjp.org/aidsgk13/ ]。会期が近づくにつれ頻繁に内容が書き換えられ、充実したサイトになりました。総会のHPですから、一定期間を過ぎると役目を終えます。しかし残しておく価値がある内容が多くあり、今後も引き続き見ることができるように工夫される予定です。 | |
| ■ 学会の働きの一つに、人の交流があります。特にロビー外交とさえいえる直接対面の情報交換は、他のどんなメディアをも上回るものです。会ってみたいと思っていた人に会えたり、新しい出会いがあったり、懐かしい出会いだったりで、これは何よりも大切です。表立ってではありませんが、参加した患者さんが休養を取ったりするための部屋が準備されていたようです。これもエイズ学会ならではの試みと言えるでしょう。 | |
| ■ 第14回学術集会・総会は速水正憲京大ウイルス研教授のもとに、2000年11月28日~30日、京都テルサで開催されます。予定表をチェックしましょう。第15回の総会長は木村 哲東大教授に決まりました。[TAKATA] |
|
|
|
広島大学医学部附属病院 輸血部 高田 昇 |
| FDAはネルフィナビルの2回投与法を認可 |
| ■ ネルフィナビル(商品名:ビラセプト、略号:NFV)は1錠250mgで、1回3錠を1日に3回、食後服用という条件で認可を受けています。11月末にアメリカのFDA(食品医薬品局)では1回5錠、1日に2回という投与法を認可しました。500人の患者に対しd4T+3TC+NFVという組み合わせで、NFVが2回と3回の投与で比較したところ、CD4数もウイルス量も差がなかったためです。NFVでよくある副作用は下痢ですが、中等度以上の下痢を経験した人も、14%と18%で有意差ではありませんでした。服薬スケジュールを簡単にすると言う意味で、患者さんにとっては朗報でしょう。日本では1回量は4錠と5錠、どちらがよいでしょうか。 |
| ネルフィナビルによる下痢にカルシウム |
| ■ ネルフィナビルは比較的飲みやすいプロテアーゼ阻害剤ですが、下痢が高頻度に起こるのが問題で、ロペミンを常用している人がかなりいます。1999年9月にサンフランシスコで開催された第39回ICAAC(Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy)では、24人の下痢患者に500mgのカルシウム錠剤を1日2回服用させたところ、下痢の頻度が33%(軽度)に減りました[抄録1308]。カルシウム剤は安くて安全なので推奨できるのではないかとのことです。 |
| ddIとd4Tの併用で膵炎による死亡例? |
| ■ ddIは商品名ヴァイデックス(一般名:ジダノシン)、d4Tは商品名ゼリット(一般名:スタブジン、サニルブジン)で、核酸系逆転写酵素阻害剤として両者の併用は広く行われています。これらの薬の副作用として、膵炎があります。膵炎では膵臓が腫れて腹痛、吐き気、嘔吐が起こり、血液検査ではアミラーゼやリパーゼという数値が上昇します。膵炎は治療しないと死亡することもあります。 |
| ■ 両方の薬を製造しているブリストル・マイヤーズ・スクイブ社では、最近アメリカで医師に対する「警告書」の手紙を送りました。アメリカではddIとd4Tに加えてハイドロキシウレア(商品名ハイドレア)を併用した患者で、少なくとも4例の死亡例が発生しています。CD4細胞数は500以上、ウイルス量も200コピイ以下と進行した患者ではありませんでした。 |
| ■ 膵炎の発生にこれらの薬剤以外の原因がないかはっきりしません。しかし、同じような治療を受けている患者は膵炎についてのモニターが必要です。もし膵炎が疑われたら投薬は中断して検査を行い、確認されたら中止する必要があるでしょう。 |
| ■ ハイドロキシウレアは慢性骨髄性白血病などに古くから使われている抗ガン剤の一種で、副作用としては白血球減少が知られています。本剤の併用は耐性HIVに対する救済療法として臨床試験が行われている途中であり、アメリカを含め世界のどこでもまだ認可を受けてはいません。膵炎の危険性については、日本でも再度注意を喚起する必要があるでしょう。 |
| FDAがヴァイデックス1回法を認可 |
| ■ アメリカのFDAは、1999年10月28日に、ヌクレオシド系の逆転写酵素阻害剤ヴァイデックス(略号:ddI)200mg錠を認可し、1日1回服用法に使用することとしました。1日に何回も、多数の薬を複雑な飲み方をしなければならない現在の治療法で、1日に1回というような簡単な飲み方に変われば、患者の服薬遵守率は向上すると期待されます。 |
| ■ これは、200mg錠を2錠服用すると言うことを意味しています。もし100mg錠を4錠としますと大きさは大きいし、緩衝剤は必要量の倍になり、下痢など胃腸障害も多くなると心配です。患者さんのQOLを考えれば、早く日本でも導入できることが望まれます。 |
| FDAはアデフォビルを不認可 |
| ■ FDAは抗HIV薬として迅速認可制度を使って申請された抗HIV薬、アデフォビルについて審議を行った結果、認可しないことを決定しました。 |
| ■ アデフォビルはGilead Science社が開発した逆転写酵素阻害剤で、これまでの抗HIV薬を使用したHAARTで治療失敗した患者を対象に臨床試験が行われました。早期の成績ではAZTや3TCに耐性のHIVにも有効性が期待されていました。FDAの専門審議会では投票を行い、13対1で申請は却下されたのです。 |
| ■ 申請された60mgの用量では、有効かつ安全とは認められなかったと審議会は述べています。アデフォビルは腎障害が問題となっており、120mgの量を使った患者で腎障害のマーカーが異常になった患者が61%発生しました。8例では人工透析が必要になりました。 |
| ■ アデフォビルは相当低い用量でもB型肝炎ウイルスを抑えるようで、Gilead Science社としては、HIVへの適応は断念し、今後はHBVでの承認を目指すものと思われます。 |
| ロデノシン(F-ddA)開発が中断 |
| ■ 新薬の開発途中に予想を上回る有害事象、特に死亡例などが発生すると、期待された新薬の開発を断念することはよくあることです。もちろん有効性が証明されない場合もあります。 |
| ■ ロデノシンはddIに類似した核酸系逆転写酵素阻害剤で、US Bioscience社によって臨床試験が行われていました。特にddI、3TC、AZTに耐性のHIVに有効という期待が寄せられていました。ところが10月13日、同社はすべての治験を中止すると発表しました。治験中に1例の死亡者があり、肝機能障害・腎機能障害例が発生した模様です。会社では治験中の全員で治験薬投与を中止し、注意深く経過観察を行うとしています。F-ddAとの関連は不明で、現在調査中とのこと。 |
| エファビレンツの評価が高まる |
| ■ エファビレンツ(略号:EFV)は非核酸系逆転写酵素阻害剤で日本では商品名ストックリンです。1999年9月には日本でも発売になりました。1日1回の服用で食事の制限がありません。副作用としては、特に最初の2週間に高頻度で起こる中枢神経障害や、皮膚障害や肝障害があります。 |
| ■ ドイツ、プエルトリコ、アメリカ、カナダの複数の施設が参加した、エファビレンツの臨床試験の成績が発表されました。450人の成人HIV感染症の初回治療として、AZT+3TC+EFVをEFV+IDV(インジナビル)、AZT+3TC+IDVを比較したところ、EFVを含む治療法の方がHIV RNA量の減少の意味でもCD4数の増加の意味でも優れ、さらに副作用によるドロップアウトも少なかったことが示されました。無作為の割付ですが、患者はどの薬かわかるものでした(N Engl J Med 1999;341:1865.)。 |
| ■ 同じ号には(N Engl J Med 1999;341:1874)小児の臨床試験も発表されています。核酸系逆転写酵素阻害剤(NARTI)服用経験がある57人の小児に、別のNARTIとエファビレンツ+ネルフィナビルの投与を行い、安全性と有効性をみたものです。結果は治療は十分に忍容でき、強力で持続的な抗HIV効果を認めました。 |
| ■ 複雑な服薬法、大量、副作用などが問題のプロテアーゼ阻害剤の使用を先に延ばすということで、非核酸系の逆転写酵素阻害剤が、今後、標準的な治療法として選ばれるようになる可能性があります。 |
|
|
|
|
| ■ 政府は感染症新法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)第11条第1項の規定に基づき、「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」を次のように策定し、平成11年10月4日、厚生大臣名で告示しました。 |
| ■ 前文に「本指針は・・・中略・・・我が国におけるHIV感染の拡大の抑制、患者等に対する人権を尊重した良質かつ適切な医療の提供等といった後天性免疫不全症候群に応じた予防の総合的な推進を図るため、国、地方公共団体、医療関係者及びNGO等が共に連携して進めていくべき新たな取組の方向性を示すことを目的とする。」とあります。 |
| ■ これに伴い、近く厚生省課長名で「特定感染症予防指針の運用について」という文書が出る予定になっています。この指針は、少なくとも今後5年間の日本のエイズ対策を規定するものです。このニュースを発行している研究班の枠組みの構想も影響を受けるでしょう。各地で活躍している人たちの法的なより所にもなるはずです。文言の中には「カウンセリング」、「NGOとの連携」、「ピア・カウンセリング」など、従来なかった踏み込んだ用語が使われているそうです。エイズ専門のカウンセラーを派遣する制度ができていない地域にも後押しになると思われます。[TAKATA] |
|
|
|
|
| ■ HIV感染症治療研究会は、「HIV感染症 治療の手引き」(A4版2色刷り、20ページ)を作成しました。HIV感染症治療を行う施設が増加している半面、施設間で治療経験や情報量の差による診療格差が生じているので、格差の是正と、早く正確にHIV診療に関する情報提供を行うためです。第1版は1999年5月でしたから、半年で改訂されたことになります。 | |||||||
| ■ 強力な抗HIV療法を早期開始することなど、8つの治療原則を示しています。個別の薬剤の説明、組み合わせ方を述べると共に、効果判定や薬剤変更の考え方を示しています。中でも不規則な服用は、治療無効になるばかりか、薬剤耐性を招いて有効な薬剤を失うことになります。このため現在の治療法では、アドヒアランス(患者自身による治療方法の決定と実践)が治療の決め手で、専門医の意見を求めることも必要としています。 | |||||||
| ■ 第2版では、ウイルス性肝炎の合併やHIV感染妊産婦の問題などにも具体的なアドバイスや治療指針を示しています。 | |||||||
|
■ HIV感染症治療研究会は木村 哲先生と満屋裕明先生が代表幹事で、白阪琢磨先生が事務局長です。
|
|
|
|
http://www.amfar.org/td |
| ■ 好評のハンドブック、「HIV/AIDS Treatment Directory」が1999年11月19日、アメリカエイズ研究財団(AmFAR:American Foundation for AIDS Research)のホームページで見ることができるようになりました。内容は簡潔にまとまっており、医療者も患者も公平に閲覧できます。HIV感染症/エイズの診断をしたら、最初に読んでみる参考書としてお勧めできるものです。 |
| ■ AmFARは1985年、俳優のロック・ハドソンの死を契機に設立され、累計160億円に及ぶ基金を集め、研究支援や患者支援を行ってきました。当初から、「HIV/AIDS Treatment Directory」という300ページ程度の本を発行してきました。年に2回も改訂されるので内容は最新です。病態生理や診断の解説は最小です。むしろ主に治療についてページを割いています。標準的な治療、実験的な治療とその成績が提示されています。薬も市販薬から、臨床開発段階のものまで掲載されています。これを見ると次に何が認可されそうかわかります。 |
| ■ 特に新薬開発のための臨床試験の最新情報(対象疾患と選択基準、プロトコル、実施機関、実施機関と連絡先)が掲載されているのは特長です。主治医や患者は、これまでの治療が失敗していても、どこにアクセスすれば挑戦できるかわかります。臨床試験をする側でも、早く適格な対象患者さんを確保することができるのです。医師よりも詳しい患者さんが生まれます。[TAKATA] |
|
|
|
これは便利! 服薬援助シート http://www.aids-chushi.or.jp/c4/fukuyaku/fukuyaku.htm |
| ■ 中四国エイズセンターのウェブページの宣伝です。ドクター・パラソルこと、兵庫医大の日笠 聡先生が作った「服薬援助シート」をご存じですか? パワーポイントを駆使したスライドショーですが、私たちはそのままカラー印刷して、マジックボードに貼り付けて外来で使っています。患者さんも医療者(医師、看護職、薬剤師)も同じシートを見ながら、薬を飲むことの相談ができます。 |
|
■ 例えば、次のような処方をしたとします。 Rx.1 レトロビル(100mg) 6 Cap/分3×28、食後 Rx.2 ヴァイデックス錠(100mg) 4錠/分2×28、食間 Rx.3 クリキシバン(200mg) 12 Cap/分3×28、8時間毎 |
| 実際に薬剤師さんはどう指導したらいいでしょうか? これを服薬援助シートに直してみたら、図のようになります。 |
 |
| 厳密に考えたら9時間も食事をとってはいけない時間があるのです。「こんなの、できません!」と叫ぶ患者さんがいるかもしれませんね。 |
| ■ 「なによりも、このシートによって処方を書く医師が、患者の服薬継続の困難さを薬剤名、用法・用量、投薬日数の4つの情報しか含まれていない処方箋よりもはるかに強く実感できることが、処方を工夫しようとする動機付けに役立ち、良い治療につながると思われます。[日笠]」 |
| ■ 服薬援助シートは薬の飲み方の理解が目的です。“なぜ薬を飲むのか”あるいは“なぜ服薬に関して厳密でなければならないのか”については、同じサイトに掲載してある患者用のパンフレット「CD4? HIV-RNA? and HAART?」、「薬剤耐性と服薬援助」も合わせてご利用下さい。ppt版はマイクロソフト社のパワーポイントあるいは、パワーポイントビュワー(無料)が、pdf版はアドビ社のアクロバットあるいは、アクロバットリーダー(無料)が必要です。Mac、Win共通です。 |
|
|
|
|
|
|
|
| ■ “エイズUpDateジャパン”の著作権は全国版とブロック版の発行者に属しますが、無断でコピイして配布しても構いません。ただし販売したり、頒価のついた出版物に一部または全部を掲載してはいけません。■ “エイズUpDateジャパン”は「エイズ治療のための地方ブロック拠点病院と拠点病院の連携に関する研究班」の事業です。研究班は3年ひと区切りですから、本号は最終号になる可能性があります。第2巻があるのかないのか、編集者もわかりません。(3年区切りの研究班なのに予算は単年度でつくというのも妙な話です。) ■ 抗HIV薬は14種類になりました。一般名、商品名、略号を薬の写真を見ながら言えますか? インターネットのHPを見てください。紙のメディアがなくなっても私たちはインターネットというメディアで続けるつもりです。[TAKATA] |
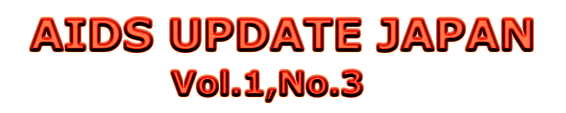 |
|
|
| ★ 1999年10月14日に、「中国四国ブロック内拠点病院連絡協議会」がKKR広島にて開催されました。この席上で「平成10年度中国四国ブロックエイズ対策事業報告書」が配布されました。この内容から“中四国エイズセンター”関係分を抜き出して、Q&A形式で紹介します。 |
|
|
| ■ 中四国エイズセンターは自称です。1997年の4月から厚生省が指定した中国四国地方ブロック拠点病院を構成する3病院(広島大学医学部附属病院、県立広島病院、社会保険広島市民病院)のスタッフにより運営されています。 |
|
|
| ■ (1)HIV感染者に対する包括的ケアを提供。(2)ブロック内の相談に応じ、患者受け入れや短期医師派遣を実施。(3)医療従事者へのエイズ教育と研修。つまり、①研修会への講師派遣と、②職種別研修プログラム(医師、看護職、薬剤師、心理職・MSW)実施です。(4)最新エイズ情報の提供。これには①ニュースレターの発行と、②インターネットのホームページがあります。(5)HIV感染症の基礎的・臨床的研究などを行っています。 |
|
|
| ■ 大半は研究費という名目です。①広島県と広島大学の受託研究契約事業(★)、②厚生省科学研究費助成金事業「エイズ治療のブロック拠点病院と拠点病院の連携に関する研究班」(▲)、③「HIV感染者の発症予防・治療に関する研究班」(▲)、④エイズ予防財団との受託研究事業(●)などの予算を使っています。広大病院関係分だけで総額2,500万円を超えています。 |
|
|
| ■ 広大病院では1998年度の新患数は11人でした。これで累計のHIV感染者数は60人となりました。患者さんの居住地別では広島県48人(外国人5人)、山口県7人、島根県2名、その他3人でした。感染経路別では輸入血液製剤(血友病)、38人、男性と性行為をもつ男性8人、異性間の性行為13人(女性4人)、不明1人でした。東京や大阪の大きな病院ではこの数倍から10倍の新患数があるそうで、広島はまだ緩やかですが、増加速度を増していると感じています。 |
|
|
| ■ 60人の患者さんのうち、13人は転居(2人の外国人は帰国)され、2人は紹介もとの病院で観察中です。転居された方、紹介もとにいる患者さん達がその後どうなったかは確実でありません。これらを除いた45人中、エイズ発病は18人で、12人が亡くなっています。12人のエイズ死亡例のうち10人に病理解剖が許可されました。最後の死亡例は1995年12月で、最近は死亡はおろか、入院数が激減しています。これは1996年から入手可能となったプロテアーゼ阻害剤をはじめとする、薬物療法の進歩によると思われます。 |
|
|
| ■ 抗HIV療法の成績はその時々で変わります。1999年4月から12月の間で最後に観察されたデータを元にご説明します。この間に29人のHIV感染者が受診していて、血友病16人、男性と性行為をもつ男性5人、異性間性行為男性5名、女性3名でした。このうち治療開始に至っていない4名を除く25人に抗HIV療法が行われています。治療期間の中央値は2,016日(範囲208~2,667)でした。この25人に投与された薬剤の組み合わせは15通りで、2剤が6人、3剤が14人、4剤が5人でした。患者毎に組み合わせを工夫しなければならないことがわかります。このうちHIV RNAが検出されているのは11人(44%)で、ウイルス学的な治療失敗例といえます。1,000コピイ未満が2名、10,000コピイまでが4人、それ以上が5人でしたが、全員で投与された薬剤を中心に耐性遺伝子の発現を見ています。CD4数が100以下の重症免疫不全の患者さんはいませんが、抗HIV療法は複雑で難しいことを痛感しています。 |
|
|
| ■ (★)1999年3月8日に、東京都立大塚病院産婦人科医長の宮澤 豊先生を講師にお招きし、病院全職員、医学部、歯学部、原医研の学生・教職員を対象にした講演会が行われました。ビデオとスライドを使った講演の他、HIV女性と妊娠・出産の問題について質疑応答が行われました。具体的なことは、実際に関係する人たちが参加したシミュレーションを行ってみて「これならできる」と感じることが大切だと思いました。 |
|
|
| ■ (★)実際にHIV感染者を診療している拠点病院に対しては、私たちの予算を使って専門医を派遣することができます。中四国地方では少数の医療者が数少ない患者さんをひっそり診療していることが多いようです。過剰な守秘体制のために医療者が孤立し、医療上で必要な連携が得にくくなりがちです。院内の症例検討会を行うことは院内カミングアウトになります。「うちの病院でもエイズの患者さんがいて、一生懸命診ているんだ」とわかることは、仲間の支援につながります。1998年度には鳥取県と山口県の病院に出向き、このような症例検討会にコメンテーターとして参加しました。 |
|
|
| ■ 中四国地方には58のエイズ拠点病院がありますが、実際に一度でもHIV感染者を診たことがある施設は半分以下です。このため各県は病院単位あるいは地域単位の病院職員を対象とした講習会に援助を行っています。中四国エイズセンターは1998年度に、合計16回ほど講師派遣をしました。ご希望の場合は各県の担当者にご連絡下さい。 |
|
|
| ■ (★)1998年度から1泊2日の看護研修プログラム(初期)を開始しました。対象は中四国ブロックの拠点病院に勤務する看護職の方です。短期間ですが1回4人の少人数で、講義と質疑、相互討論、教材の配布、ビデオ学習、外来診療見学、患者さんとの対話、まとめの討議など盛りだくさんです。心理的な支援については、財団のブロック研修に委ねています。1999年度も継続して実施されています。受講者募集の案内は各県から病院の院長、看護部長あてにお送りします。 |
|
|
| ■ (▲)自発的なものですが、薬剤師がHIV感染者に対し有効な服薬援助活動を行うことができること、また共有できるツール類の作成を行うことを目的に、3病院の有志の薬剤師を中心に月例の勉強会が始まっています。抗HIV薬、日和見疾患治療薬の種類や使い方、特に副作用と相互作用が大切です。地域で集まるのがよいと思います。 |
|
|
| ■ (▲)中四国では研究班の資金援助で研修会を開いています。エイズ拠点病院に勤務する薬剤師が、適正に抗HIV薬の服薬援助活動ができるようになることを目的に、「薬剤師の抗HIV薬服薬指導のための研修会」を開催しています。1泊2日で、招待講師の講演や実際に服薬をしている患者さんの話、そしてロールプレイによる服薬支援の実習を行います。1998年度は2回で総参加者数は57施設、60人でした。1999年度も継続しています。開催の案内は院長と薬局長あてにお送りしています。 |
|
|
| ■ (●)エイズ予防財団が主催するカウンセリング研修会は、2泊3日コースで、毎年4回開催されています。各県から毎回、拠点病院に案内が送られていますが、希望者が多く、何人かは断られます。中四国エイズセンターのスタッフは、指導スタッフとして参加しています。これとは別に、やはり財団の支援を得て、四国ブロックと中国ブロックで別々に毎年1回、各県まわりもちで1泊2日のカウンセリング研修会が行われています。1998年度はそれぞれ高知市と山口県小郡市で、30人から40人の規模で行われました。 |
|
|
| ■ (▲)1997年から「中四国エイズセンター・ニュースレター」を合計4号発行しましたた。1999年度からは、この「エイズUpDateジャパン」として全国配布されることになりました。中四国ブロック版の印刷数は1,000部となり、関係医療機関、保健所、医師会、歯科医師会、NGOなどにお送りしています。 |
|
|
| ■ (★)私たちが診療している患者さんの半数がインターネットをしています。一般にネット上の情報は色々なものが混在しており、内容がいつも正しいということは難しいものです。取捨選択は自己責任に属すると思われます。1998年1月末に公開して以来、「中四国エイズセンター」のホームページ(http://www.aids-chushi.or.jp)の総アクセス数は、1999年3月には22,000、11月には40,000を越えました。「エイズ関連用語集」はよく利用されているようです。イベントカレンダー、エイズ文献紹介や最新ニュースなど、頻繁に内容を更新しています。 |
|
|
| ■ (▲)一番気になっているのは「薬は増えたけど本当に患者さんの役に立っているのか」ということです。「薬剤耐性HIV遺伝子に関する臨床的研究」は国立感染症研究所や全国の多数施設と共同研究をしています。耐性検査の解釈は難しいのですが、細菌や結核菌と同じような意味がありそうです。また「プロテアーゼ阻害剤の血中濃度に関する臨床的研究」については、トラフ値の比較ではありませんが、血中濃度にはかなり個人差がありそうだとわかりました。 |
|
|
| ■ (▲)血漿は単なる通り道であり、HIVの本拠地はリンパ装置や白血球の中です。量的な変動はどうでしょうか? 「末梢血単核球中のプロウイルスDNAおよびメッセンジャーRNAの臨床的意味」について藤井Drが検討を行っています。抗HIV薬を開始すると、血漿HIV RNA値はすみやかに低下しても、細胞内のmRNA量の低下速度はゆるやかで、プロウイルスDNAの低下は非常に遅いものでした。抗HIV薬によるHIVの排除は非常に困難で、極めて長期戦であると推測されます。これらの成果の一部は第12回国際エイズ会議(1998年7月、ジュネーブ)や日本エイズ学会で報告しました。 |
|
|
| ■ 1998年度までの国内統計によると、日本の人口の10分の1を占める中四国9県では、輸入血液製剤によらないHIV感染者/エイズ患者の全国比率のわずか1.6%しか診ていません。しかし日本でも都会からジワジワと広がっています。感染から症状が現れる状態になるまでに時間のずれがあるため、エイズが増えているかどうかの実感は難しいものです。どの程度まで増えたら横這いになるかは不安定要因が多くわかりません。 |
|
|
| ■ 学会や専門誌では急性感染の症例報告が増えてきました。エイズ発病で感染がわかる例の比率が高くなっています。これらは氷山の一角です。献血者におけるHIV抗体陽性率の増加も冷酷な事実です。社会全体が「薬害エイズが終わったら日本のエイズは解決した」かのような無関心に陥っています。感染拡大を抑制できる因子が何もないことが一番の根拠です。ここ10年20年の単位で増えていくことは残念ながら確実だと言わざるを得ません。 |
|
|
| ■ エイズという新しい病気に対処するために、純粋に人員増加がはかられたのはエイズ治療研究開発センターです。ブロック拠点病院ではリサーチレジデントという非常勤職員がつきました。残りはそれまでに配置されている職員にエイズの仕事が被さっています。いつまでか、どこまでかという達成目標が作れません。いつ消滅するかわかりません。政策医療の実施のために事業費ではなく、研究費が使われていることの矛盾を感じています。 |
|
|
| ■ 医療の面ではエイズが普通の病気になって、特別な体制を作らなくても自然に医療連携がはかれて良質のケアが提供できればいいのでしょう。そこまでに至るには組織的な基盤の強化が必要です。他の仕事の片手間ではなく、感染症科などエイズ診療を標榜できる診療部門の立ち上げが必要かもしれません。さらに治療のみではなく、感染疫学や予防の専門家や地域のNGOと一緒に仕事をすることが、長い目では大切ではないでしょうか。[TAKATA] |
|
|